| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第1章「夢のはじまり」 | ノベルトップ |
| 第1章 夢のはじまり |
無明の空間で混濁するおぼろげな意識。 二つの影絵人形が舞踏する姿に合わせて、楽師たちの奏でる調べが忘却した記憶を呼び起こすように脳内で木霊する。 それは幻聴か幻視か、紅玉が艶やかに燦然と耀くよう、華やかな舞踏会は紅く燃え上がった。 鋸を引くような猛悪な演奏の中で、紳士の影絵人形が暗冥の魔獣に変貌し、次々と淑女たちを喰ろうていく。 切り離された腕や脚やはたまた首が、回転木馬のように目まぐるしく廻る。 柱時計の振り子が刻む音。 頭が割れるほどに響き渡る鐘の音の遠く先で、微かに聞えてくる映写機の廻る音。 無機質な演劇は機械的に進み、やがて朱に染まった世界は、樹脂が溶けるように穴を開けながら崩れていく。 紅蓮の炎に包まれた淑女が自らの頸部を押さえ、藻掻き苦しみながら死の灰となって舞い上がった。 その光景をただじっと丸い瞳で見つめていた少年……。 「母さん!」 その若者は冷たい寝汗を掻きながらベッドから跳ね起きた。 とても嫌な夢を見たような気がしたが、まるで頭の中に靄がかかったように何も思い出せなかった。ただ、嫌な夢だったという印象は強く残り、手に握る冷たい汗と胸がむかつく吐き気が、証拠として今も如実に残っている。 若者は汗を拭こうと額に手を伸ばした。するとそこに違和感を生じ、目隠しのような物があることに気付いたが、開けている視界から察するに目隠しではなく別の物。不審に思いながらそれを外そうとすると、「外してはなりません」と若い女の声がした。 「なんだ!」若者は振り返り震える声をあげた。「すまない、急に大声を出してしまって、それにしてもあなたはいったい?」すぐに詫びを入れたが、その瞳は泳ぎながら奇異な色で女を見ている。 異様とも言える女の姿は誰もが驚きで息を呑むに違いない。使用人風のエプロンドレスを着た首から下は特段に目を引く物ではないが、問題はその首から上の頭部全体を覆う黒いフェイスマスクである。目と口の部分だけが覗くそれは異種異様であり、まるでギロチン刑の処刑人が顔を隠しているようで、悪辣で背筋を走る寒気が全身を硬く凍らせてしまう。 どこやらここは屋敷の一室のようである。建物の造りは野暮ったく、柱や壁に装飾などないのだが、置いてある家具などは優美で繊細な曲線で装飾され、ロココ様式を意識した物ばかりで埋め尽くされていた。見る者が見れば屋敷の趣向と家具が不一致であると感じてしまうだろう。 使用人風の女は若者の目の前に手鏡を出した。「そのマスクは決して人前で外さぬようにお願いします。それがこのお屋敷での決め事でございます」 目の周りを覆う白いマスクは質素な作りで、その一部を隠すだけで顔全体を無機質に見せる。 混乱する若者の頭。自らの頬や鼻筋、髪の毛に至るまで触れてみた。言い知れぬ恐怖に若者は気付いてしまった。 ――マスクの下にどんな顔があったか思い出せない。 そればかりではなく、自分はいったい何者か、この部屋がどこなのか、過去のことも何一つ覚えてない。顔を見れば手がかりがと思い、手に汗を滲ませながら慌てて若者はマスクを取ろうとした。だが、女に手首を掴まれ制止させられてしまう。 「決して人前では外してはなりません」淡々とした口調。 若者は焦る気持ちを抑えながら、マスクから手を放して女の言うことを聞いた。 少し若者は苛つく口調で「なぜ外してはいけないんだ?」と尋ねると、女の口元が微かに震えた。 黒いフェイスマスクから覗く眼と口は、顔の全体像が見えるときよりも強調され、微かな感情の変化もありありと映し出される。顔全体が見えていれは気付かなかった女の動揺。口元の震えは果たして何を意味しているのか。 しかし、女の声音は淡々たるものだった。「お館さまのご命令です」 「お館さまとは、ここはいったいどこ……いや、それよりも僕はいったい誰なんだ?」 若者が記憶を失っていること知らなければ、聞いた方はおかしな質問だと戸惑うだろう。自らもそのことに気付いて若者は言い直した。 「実は記憶がないんだ。ここで目を覚す以前のこと、自分が何者で何をしていたのか、名前すら思い出せない。僕はいったい誰で、どうしてここにいるか教えてくれないか?」 「貴方様が何者であるかわたくしは存じ上げません。この屋敷に滞在する者は自らの素性を明かさないというのも、決め事の一つとなっておりますから。わたくしはお館さまから貴方様のお世話を任された召使いに過ぎません」 マスクと素性を明かさないという決め事。異様さを感じずにはいられない。なぜそんな場所に自らがいるのか若者は理解に苦しんだ。 「僕の世話を任されていると言ったが、どのくらいここに滞在していて、僕が君に今までどんなことを話したか教えてくれないか? 何か記憶を取り戻す手がかりがあるかもしれない」 ベッドで目が覚めたのだから、この屋敷で過ごした時間がある筈で、世話係の女とも何度か顔を合わせて、会話の一つや二つしているに違いない。だが、女の言葉は全てを裏切った。 「貴方様とお話させていただくのは、これが初めてでございます。なぜなら貴方様はわたくしが世話を任されてから、もう三日もこのベッドで寝たきりで目をお覚ましになられませんでしたから」 「どういうことだ?」 「わたくしはただの召使いに過ぎません。答えられることには限界がございます」 知っていて答えないのか、それとも本当に何も知らないのか。 若者の頭の中で質問が頭痛を引き起こすほどに木霊する。山のように訊きたいことがある。自らの記憶を取り戻す手がかりになりそうなこと、今置かれている環境について。この召使いの女は若者の素性を本当に知らないのか、それはわからないが、答えない以上は質問しても無駄であるから、別のことを尋ねるのが妥当だろう。 「この場所はどこで、誰の屋敷で、君の答えられる範囲でいろいろ教えてくれないか?」 「お館さまは……」少し口ごもる様子を見せながら、言葉を続けた。「マダム・ヴィーさまでございます」 「ヴィーとは変った名だな」 「名前ではなくアルファベットでございます。この屋敷では本名を口に出すことが禁じられているため、滞在する者も含めて皆、アルファベットで呼び合うことになっております」 素性を隠すためだけにしては、マスクと言い異様な決め事だ。 さらに召使いの女は言葉を続ける。「まだ貴方にはアルファベットがございません。アルファベットはお館さまが付けてくださいます」 「君にもアルファベットがあるのか?」 「いいえ、わたくしはただの召使いに過ぎません。人間以下のわたくしたちは、単純に識別するためだけに番号で管理されております。わたくしの場合は二号と」 人間以下……屋敷の主は人格者ではないのだろう。二号の異様な格好を見れば、〝束縛〟されていることは容易に想像できる。フェイスマスクは拘束具の一種であり、それは肉体を支配する物であるが、二号は心までも〝拘束〟されている。それは〝お館さま〟と呼ばれる者の話題をするときの態度を見れば明らかだ。 おそらくお館さま――マダム・ヴィーはこの屋敷に置いて絶対的な権力を持っている。もしかしたら、その影響力は屋敷の外にまで及んでいるのかもしれない。それを想像する根拠は、滞在者にも異様な決め事を強要することだ。若者の素顔を隠す無機質な仮面。 異様な決め事はマダム・ヴィーの趣向か、それとも深い意味が隠されているのか。根拠や物証のない推測は、正しい答えを見いだすには及ばない。現時点での推測はあまり意味のあることではないだろう。多くの謎はマダム・ヴィーに尋ねるのが筋であり、若者が何者であるかという答え、もしくはそれを導く手がかりは、おそらくそこにある。 「マダム・ヴィーに今すぐ会いたいのだが?」若干、焦る口調で申し出た若者。 「……おそらく、今は誰ともお会いになられないと思います」答えるまでにあった数秒の黙しから、異様な空気を感じ取ることができた。その黙しの最中、これまでになく唇を振るわせていたのだ。 まるで問い詰めるように「なぜ?」と強い口調で若者は尋ねた。 しかし、二号はその問いかけに答えることなく、「夕食のときにお館さまとお会いできます。それまでにお着替えになって、身支度を済ませておいてください」 「夕食か……」 若者は大きな窓の外に視線を移した。 空は夕闇に染まり、沈みゆく朱色に蒼の闇が覆い被さっていた。 ぼんやりと外を眺めていると、何か扉のようなものが開く音が若者の耳に届いた。そちらに顔を向けると、二号がクローゼットを開けて立っていた。 「お着替えはこちらにご用意してございます」 「用意がいいな」 良すぎると言ったほうがいい。用意されていた服は一つや二つではなく、クローゼットいっぱいに服が詰まっていた。この待遇の良さに疑問を感じずにはいられない。 目を覚ましてから疑問ばかりだ。 時折、隠し事があるようなそぶりを見せる二号の言葉を、すべて信じることは心情的にどうしてもできないが、嘘をついているという確証もない中で、今までの会話をすべて鵜呑みにするのならば、三日の間は寝たきりで目を覚まさなかったという。そして、若者と話をしたのは、先ほどが初めてだと言った。 この屋敷にはいつからいるのだろうか? 三日間は寝たきりで、それ以前は会話を交わしたことがない。 記憶を失ったのはいつ、〝どの場所〟だったのか? 二号はすでに部屋を出ようとしていた。 「では、お食事の時間に呼びに参ります」 軽い会釈をして部屋を出て行く二号の背中に「まだ……話が」若者は声を掛けたが、扉の閉まる音が虚しく響いた。 部屋に独り残された若者は、しばらく難しい顔をして立ち尽くしていたが、急に歯切れよく動き出してクローゼットの中を物色しはじめた。 この衣服は若者の為だけに用意されたものなのか、はじめから屋敷にあったものかのか、それとも……という考えが脳裏に過ぎる。その考えとは、自分の持ち物なのではないかという予感である。なぜそう思ったのか、確証があるわけではないが、しいていうならば直感でそう感じた。 いくつかの服を見たが、若者はすぐに着替えることはしなかった。 部屋を軽く見渡して、何かを探すようなそぶりを見せる。物を探すと言うより、部屋を見取るように眺めている。 「シャワールームはないのか?」 呟いて若者は歩き出した。 三日間、寝たきりであったのならば、シャワーも浴びて汗を流したい。それとシャワールームの近くには鏡がある筈だ。手鏡は二号がなぜか持っていってしまったらしく、自分の素顔を見るためにどうしても鏡を探したかった。 若者は歩きながら自分の手や腕の臭いを嗅いだ。ほのかに石鹸の匂いがする。続いて、髪の臭いも嗅いでみた。まるで洗い立てのような、芳しい花の匂いがした。 寝ている間に体を洗われていたと考えるのが自然だろう。ならばシャワーを浴びる必用はないが、鏡は見つけ出さなくてはいけない。 部屋を移動してすぐに洗面台を見つけることができた。その場所に鏡はなかった。代わりに壁には、そこにあった物を外したような跡が残っていた。おそらく鏡を外した跡だ。 しかし、どうして鏡を外す必用があったのか? 何らかの理由、例えば割れた鏡を取り替えるために、そこにあった鏡を外したと考えるのが、普段の生活では考え得ることだ。が、疑惑ばかりのこの状況では、勘ぐってしまわずにはいられない。 「僕に見られてはいけないモノがある……素顔」 例えそうであったとして、理由が不明瞭である。 人前では仮面を外してはいけない。その決め事と関係があるのか、それとも……記憶を失っていることに関係があるのか。 記憶を失った原因は何か? 若者は考えを巡らせることに没頭して、ふと我に返ったときに、無意識のうちに腕を掻いていることに気付いた。掻いていたのは腕の裏側。爪で引っ掻いて赤くなったその場所に目を凝らした。 眉を寄せて怪訝な表情をした。 まるで虫に刺されたような痕が一つあり、少しずれた場所にもう一つ。ここで若者は急に首に手を当てた。そこにもあった、指先に触れる痕の感触が首にもあったのだ。 視界が瞬間的な転換を起こし、脳裏に刹那、艶やかな唇が浮かんだ。 妖しく嗤う女のルージュ。 何か思い出せそうになった瞬間、若者の頭が急に痛み出し、辺りが急に白い靄に包まれ、そして闇に沈んだ。 夢の館専用掲示板【別窓】 |
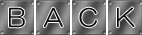
| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第1章「夢のはじまり」 | ▲ページトップ |