| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第3章「Jの視線」 | ノベルトップ |
| 第2章 Jの視線 |
七時ちょうど、全員が食卓に着くと料理が次々と運ばれてきて、マダム・ヴィーの合図で食事がはじまった。 若者は料理に目もくれず、マダム・ヴィーに話しかけた。「まだ目が覚めたばかりで困惑す ることばかりです。大変申し訳ないのですが貴女のこともよくわかりませんし、実を言うと事 故のこともよく覚えていないのです」 なぜかマダム・ヴィーの唇が微笑みを浮かべた。「あんな事故に遭ったのだから無理もないわ」 「あんな事故?」 「狩猟の最中、崖から転落したのですわよね、G?」マダム・ヴィーはGに顔を向けた。 「マダム様の言うとおり。獲物に気を取られた俺が崖から足を滑られて、助けようとしたお前といっしょに落ちちまったってわけさ」 間髪入れずマダム・ヴィーが続ける。「そこへわたくしの召使いが偶然通りかかり、意識を失い怪我をした貴方たちを見つけたということよ」 筋は通っている。 しかし、記憶を失っている若者としてみれば、どんな説明を受けても確信は得られない。 今はより多くの情報を手に入れ、記憶を呼び起こす手がかりにするほかあるまい。 「僕たちを見つけてくれた方に礼を言わねばなりませんね」 「うふふふ、召使いに礼だなんて、おもしろいことを言うのね」一笑したマダム・ヴィー。 若者は相手の地位に関係なく、命の恩人に礼を尽くすのは当然だと思いながらも、あえて反論は控えた。 「しかし、事故のことを詳しく知りたいので、その召使いに会いたいのですが?」 「どの召使いだったかしら……あとで話を付けて置くわ」 おそらく彼女にとって召使いは皆同じ、そのためにどの召使いが何をしたかなど、覚えてもいないのかもしれない。 「ありがとうございます」若者は礼を言い、「ところで、この屋敷には僕とG以外にも何人か客人がいるようですが、いったい何の集まりなのでしょうか? 部外者の僕らがいてはお邪魔なのではないかと」 「気にしなくていいのよ。集まりなんてたいそうなものではないわ。ただの静養で訪れているだけなのだから……」 マダム・ヴィーの言葉には含みがあるような気がする。 赤ワインを片手にJが話に割り込んで来た。「マダム・ヴィーの言うとおりさ。ここはいつでも客人を歓迎してもてなしてくれる。おかしなルールもあるけど、ほんのお遊びのようなものさ」 おかしなルール――マスクやアルファベットの名前のことだろう。そう言えば、若者にはまだアルファベットが付けられていなかった。 マダム・ヴィーはそのことを思い出したらしく、「そうだわ、まだ貴方には名前がなかったわね。そうね、Aなんてどうかしら、貴方にぴったり。それ以外に考えられないわ、Aに決めましょう。今このときから、貴方はAよ」 ――A。 マダム・ヴィーの独断で決められたアルファベット。何を理由にAと名付けられたのか、それはマダム・ヴィーのみが知るところだろう。 Aと名付けられた若者。記憶を失い本当の名前すら思え出せない彼には、仮の名前が与えられることはちょうどよい。決め事があれば本名を尋ねられることもなく、それによって口ごもる心配もないだろう。 しかし、「改めてよろしく〝A〟」とJに挨拶されたが、Aになったばかりの若者は反応に遅れてしまった。 「ああ、僕のことか。まだ慣れないモノで申し訳ない。こちらこそよろしく」 AとJはワインを酌み交わした。 さらにマダム・ヴィーが祝杯をあげる。 「名前も決まり、正式な客人としてAを迎え入れましょう。わたくしの屋敷では自由にしてもらって構わないわ。ただし守るべき決め事は守ってもらえなければ、客人としてもてなすことはできないわ」いくつかの決め事とその理由を述べる。「人前では決して仮面を外し素顔を晒してはいけない。本名を名乗る行為もこの屋敷では固く禁じるわ。なぜなら皆さんには表社会での地位や身分を忘れ、この屋敷での夢のような時間を過ごしてもらいたいからよ」 それはまるで仮面舞踏会。 決め事の裏を察するならば、この屋敷に滞在する客人たちは、高い地位や身分の者たちなのかもしれない。 急な客人であるAとGを抜かし、正式な客人としてこの場にいるのはJである。歳は若いように思えるが、このJも何かの事業主か、あるいは跡取りなのだろうか。 ほかの客人――食事の前に癇癪を起こして立ち去ってしまったSという女。そして、まだ見ぬMという女。本人が資産家でなくとも、生まれた、もしくは嫁いだ家柄が良家である可能性もあるだろう。 そもそもこのような屋敷に住むマダム・ヴィーと親交がある時点で、それなりの地位や身分のある者たちなのだろう。本来ならばAやGがいることは場違いであり、なぜマダム・ヴィーは二人を客人としてもてなしてくれているのか。それは事故に遭った不幸な者たちだからか、それとも身分の違いなど関係ないという寛大な心を持ち合わせているのか。 しかし、これまでのマダム・ヴィーの態度から察するに、彼女は召使いたちを同じ人間だと思っていないのだろう。つまり彼女は身分の違いによって人を蔑む。たしかにAとGは召使いではないが、実際にところはどう思っているのか。 Aはあまり食が進まなかった。不安が喉を詰まらせる。記憶を失っている上にこの環境、無理もないだろう。ワインばかりが進んでしまう。 マダム・ヴィーとJはたわいない談笑に華を咲かせている。一方、GはAよりも早くワインを空けていく。まるでその飲み方は水でも流し込むような勢いだ。 「そんなに飲んで平気なのか?」少し心配そうにAが尋ねた。 するとGは「なんだか傷が痛むんで、酒で紛らわせようと思ってな」と頬を真っ赤にしながら答えた。 傷とは頭の傷のことだろう。傷口がどの程度の物かわからないが、あの包帯の様子から見て、大きな怪我だったのかもしれない。 急にGが頭を振り子のように回したかと思うと、次の瞬間、食器やグラスを倒しながら大きな音を立て食卓に頭から突っ込んだ。 「おい、大丈夫かっ!」慌てて声をかけるA。 料理が散乱し、硝子や陶器の食器も割れ、溢れたワインもテーブルクロスに赤い染みを広げた。 何事かと場は騒然としたが――実際に慌てた様子を見せたのはAだけであったが、Gは自らの力で上体を起こし、少し悪びれた様子で平謝りをはじめた。 「すまん、すまん。少し飲みすぎたみたいだ」そう言いながら席を立ち、「先に部屋で休ませてもらう」軽く頭を下げて挨拶をすると、おぼつかない足取りで、すぐに駆けつけた召使いに肩を借りながら食卓を後にしてしまった。 Aも席を立った。 「友人が心配なので僕も失礼します」 理由をつけて食卓を後にした。 Gの身を案じているのは本当だが、それは記憶の鍵を握るのがGだからだ。 後を追ってすぐに廊下に出たつもりだったが、すでに人影もどこにもなかった。 広い屋敷だ、どこを探してよいのかもわからない。こんなことならば、先に部屋の場所を聞いておくべきであった。 当てずっぽうで歩き出してしばらくすると、「どこにおいででございますか?」と後ろから声がした。 今まで気配などしなかったのに、にも関わらず振り返るとフェイスマスクの召使いが立っていた。この召使いの声と背格好には覚えがある。おそらく二号だ。 「友人のGが体調を崩して、心配だから彼の部屋に様子を見に行こうと思ったのだけれど、どこに部屋があるのかわからなくて困っていたところなんだ」 不自然な理由ではない。だが、AはあわよくばGの酔いを覚まして、自分のことなどいろいろな話をするつもりであった。 この二号には記憶を失っていることを不意に打ち明けてしまったが、今考えると軽はずみな行為だったことは否めない。疑念――もはや疑惑ともいうべき、置かれている環境を考えると、こちらも不審な行動は悟られたくはない。すでに記憶を失っている話は、二号からマダム・ヴィーに伝わっているとも考えられるが、念を押した行動を続けるべきであろう。 二号はAの前を歩き出した。 「G様のお部屋はこちらでございます。ご案内いたします」 「それはありがたい」 Gの部屋は一階にあった。二階にあるAの部屋とは真逆の位置ともいうべき場所。 扉の前に立ったAはノックをした。 しばらく様子を見て待ったが返事はない。だいぶ酔っていたようなので、この程度では気付かないのかもしれない。 「おい、いないのか!」少し声を張り上げ、そのままドアノブに手を掛けた。だが、開かない。鍵が掛っているのだ。 そこで二号が、「もうお休みになられたのでしょう」 「たしかに……だいぶ酔っていたみたいだから、横になってすぐに寝てしまったのだろう」 焦ってはいけない。どうせ酔った状況ではまともな話もできなかっただろう。明日まで待とう。 「僕はこれから屋敷を少し見て回ろうと思う。ここまでありがとう、もう一人で大丈夫だから」 「ご案内しなくても宜しいのでしょうか?」 「いや、結構。少し見て回るだけだから、自分の部屋の場所もわかっている」 「そうでございますか。一つだけご忠告がございます。地下は古くなっていて、普段から使われておりません故、危のうございますから無闇に近づかぬようお願いいたします」 「ああ、気をつけるよ」 勘ぐってしまうのは致し方ないことだろう。そう、地下のことだ。考え過ぎかもしれないし、もしも何かあるとしても、どちらにせよ無闇に近づくことは好ましくない。 Aは二号に別れを告げ、赴くままに歩きはじめた。 まだ夕食は続いているのだろうか。それならば、マダム・ヴィーと会話をするのもよいだろう。 食堂に向かう途中、サロンの横を通りかかると、猫脚椅子に座りながら優雅にティーカップを持つJの姿が見受けられた。 向こうもAに気付いたらしく、「どこに行くんだい?」と尋ねてきた。 「食堂にはまだマダム・ヴィーはいらっしゃいますか?」 「いや、もう彼女はいないよ。一度彼女を見失うと、どこでなにをしているのか、屋敷の中を探すのは大変だろうね。まあ彼女に用事があったのかもしれないが、あきらめてボクと少し会話でもどうかな?」 「たいした用事はなかったので……」そう言いながら、AはJの近くの椅子に腰掛けた。 Jはテーブルに置いてあった空のティーカップに紅茶を注ぎはじめた。 「紅茶でよいかな?」 「はい」 「そう固くならずに、気軽に接してくれて構わないよ」Jは紅茶をAの前に置きながら、口元に微笑みを浮かべた。 しかし……。 Jを見つめるAの視線。 「ボクの顔になにか?」 尋ねられてAは首を横に振った。「いえ、別になにも……」 マスクに浮かぶJの瞳。はじめて会ったときには気付かなかったが、まるで何かを射貫くような鋭い眼。口元に笑みを浮かべ、柔和な雰囲気を醸し出しているが、眼のずっと奥にある〝何か〟が、〝違う〟と物語っている。 果たしてこの男は何者なのか。 何をしゃべろうかとAが悩んでいると、先にJが話を切り出した。 「この屋敷には多種多様な職や地位に就いている者が集まってくるのだけれど、君は普段なにをしているのかな?」 「それは……」 記憶にないことは答えられず、口ごもってしまった。 「すまない、この屋敷であれこれ人のことを詮索するのは御法度だったね。しかし、少しくらい決め事を破ったところで、別に構いはしないだろう。そうだね、ボクのことを話そうか」 Jのしゃべり口は実の饒舌であった。 自分のことに答えたくないこと、Aの場合は記憶にないからなのだが、そういう場合は決め事を盾にすれば回避できそうだ。 紅茶で喉を潤してからJは話を続けた。 「この屋敷に来る客人たちの中にはいけ好かない貴族たちも多いが、ボクは元々貴族の出身ではなくて、いわゆる成り上がりで財を築かせてもらった。主に貿易関係の仕事をしているのだけど、土地の売買などもやっていてね。会社のほうはボクがいなくても軌道に乗っていて、このように悠々自適に過ごして居るんだ」 「この屋敷にはよく?」 「そうだね、一年のほとんどをここで過ごしているんじゃないかな」 ならば、おそらくこの屋敷のことについて精通しているはず。マダム・ヴィーともかなり親しい間柄の可能性もある。 次のAからの質問はすでに決まっていた。 「マダム・ヴィーとの付き合いも長いのですか?」 「いやいや、まだ三年ほどかな。ボクが知る限りでは、SやM女史のほうがマダムとの付き合いは長いだろう。なにせボクがこの屋敷を訪れるようになったころには、すでに屋敷に住んでいたみたいだからね」 滞在しているのではなくて、住んでいる。ただの客人ではないのかもしれない。 Sはすでに会ったが、Mについてはまったくと言って情報がない。 「まだMとはお会いしてないのですが、どのような方で?」 「あまり自分のことを語りたからず、人と関わることも好きでないらしい。ボクもあまりしゃべったことがないね。本人に会って見るのがよいよ」 「そうですか」 機会が会ったら話をしてみよう。 今は周辺の人間たちよりも、この屋敷の主を先に知る必用があるかもしれない。 「マダム・ヴィーについて詳しく知りたいのですが? このような屋敷に住み、いったい何者なのだろうかと」 「ふふっ」Jは少し笑った。「この屋敷ではあまり人のことを詮索するべきではないよ。とは言うものの、ボクはそういうのが嫌いじゃない。ここだけの話だよ」と言って、Jは唇の前で人差し指を立てた。 Aは息を呑んで深く頷いた。 するとJは今まで以上に饒舌に語り出した。 「マダム・ヴィーというのはもちろん偽名、召使いたちにはお館様と呼ばれているのは知っているかな?」 「ええ」 「まるでこの館の主であるがごとく振る舞い、客人たちもそう思っているだろう。しかしね、実際のところを言うと、彼女はただのマダムに過ぎない。この一帯を治める領主の夫が存在していて、その者こそが正当なこの屋敷の主であり、絶対権力者なのだよ。ボクは領主Xと呼んでいるが、そのベールは謎に包まれている……マダム・ヴィーの素顔のようにね」 「主が別にいる……」 「しかし、領主Xについてはあまり口に出さない方がよいだろう、特にマダム・ヴィーの前では」 「どうして?」 「理由はわからないが、領主Xの存在自体を隠蔽したいらしいことは間違いないね」 なぜ、Jはここまで知り得ているのか、疑念が浮かぶ。 「まさか貴方はマダム・ヴィーの愛人なのでは?」 「あははは、まさか。私がマダム・ヴィーの愛人? とんでもない、彼女と付き合えるのは悪魔だけさ」 口元は戯けたように笑っているが、マスクの奥にある瞳は冷たい視線を放っていた。 記憶を失ってから、信じるべきことがなにかわからない。言葉など、嘘をつくのはたやすい。 そう言えば、何もない可能性もあるが、あのことも聞いておこう。 「この屋敷の地下にはなにがあるか知っていますか?」 「さて……なにがあるんだろうね。見てはいけない〝モノ〟があるのかもしれないよ、ふふふっ」 その口ぶりは何か知っているのかもしれない。やはり、Jはこの屋敷の内部事情に精通しているらしい。 急にJが熱っぽい視線をAに向けた。 「さて、ボクはいろいろ話したよ。今度はキミの番だよ、ボクはキミのことをもっとよく知りたいな」 忍び寄ってきたJの手が、Aの手に軽く触れた。 異様な雰囲気がした。 Jの顔がすぐ目と鼻の先まで近づいてくる。 驚いたAは席を立った。 そして、自分を見つめる視線がJだけでないことに気付いた。 いつの間にか柱の陰に立っていた二号の姿。まさか、監視されているのか。 さらに、もう一人。 車椅子に乗って現れたルージュの貴婦人――マダム・ヴィー。 まるで何かを思い出したように、「そろそろ僕は部屋に戻ります。それでは……マダム・ヴィーも失礼します」Aは逃げるようにこの場を後にした。 夢の館専用掲示板【別窓】 |
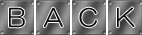
| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第3章「Jの視線」 | ▲ページトップ |