| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第4章「死の舞踏」 | ノベルトップ |
| 第4章 死の舞踏 |
紅い口紅で描かれた夢物語。 仲むつまじい家族の情景。 父と母の間に挟まれ、両の手を優しく繋がれた幼い子の姿。 そこへ現れる一匹の魔獣。 炎を身に纏う魔獣が、紅玉の眼を輝かせながら、全てを呑込んでしまう。 嗚呼、どこかで舞踏会の音楽が聴こえる。 「……夢……を見ていたのか?」 ベッドに横たわりながら、Aは天井を眺めた。 記憶は未だ戻らず、今見たばかりの夢のことすら思い出せない。そう言えば、昨日も夢を見たような気がする。おぼろげに、どちらも嫌な夢であったと、微かに不快感が残っているのみ。 マスク……そうだ、昨日はなぜか部屋に戻ってきた途端に睡魔に襲われ、このマスクを外すことすら忘れていた。今ならば誰も見ていない。 隠された素顔。 もしも、素顔を見たとき、なにも思い出せなかったら? 恐ろしい、それほど恐ろしいことがあるだろうか。それならば、いっそのことマスクを外さない方がよいのではないか。 しかし、内から沸き上がる衝動を抑えることは出来ない。 なにか、そう、鏡になるような物はないだろうか? 生憎、この部屋には鏡やそれに属する物はない。ご丁寧なことだ、それほどまでに素顔を見せたくないのか。やはり、見なくてはならない。 窓がある。夜ともなれば鏡の代わりになるが、まだ陽が高く映りが悪い。だが、微かに写るその姿でも……見たい。 Aは窓の前に立ち、マスクに恐る恐る手を伸ばした。 「なぜだっ!」 嗚呼、なんということだ。Aは叫び声を上げた。 想像もしていなかった。 マスクが、マスクが外れないのだ。 まるで皮膚の一部となってしまったかのごとく、外そうとしても痛みが走るほどに密着している。 「どうして、どういうことだッ!」 やはり、これは決定的だと言わざるを得ない。 疑念が確証へと変る。 ただ、それは悪意なのか、敵意なのか、それとも別の何かか。 「崖から落ちただと……信じられるかそんなこと。どうして僕は記憶を失ったんだ!」 Gに話を聞く必用がある。あの男はいったい何者なのだ。あの男だけではない、この屋敷にいる全ての人間だ。 崖から落ちて気を失ったというのに、無傷というのも信じられない。怪我をしたというGのあの包帯も偽装ではないか、全て作り話なのではないか。 嘘偽りならば、そこには理由がある筈だ。 「……落ち着け」 そう、慎重にならなくてはいけない。 〝相手〟の目的がわからぬうちは、軽はずみな行動は控えなければ。 Aは着替えを済ませ、平静を整えると部屋を出た。 まずはGの部屋に向かうことにしよう。もう昨日の酔いも覚めている筈だ。 廊下に出てしばらく歩き、階段まで差し掛かると、テラスの方から何やら騒がしい音が聞えてきた。 不審に思いながら階段を下りずにテラスへ向かうと、騒がしさは下から聞えてくるようだった。身を乗り出して庭を覗くと、そこには――。 「……まさか」 地面に不自然な格好で横たわるGの姿。 その近くには召使いたちやJが人だかりとして集まっているようだった。明らかに事故の様相を呈している。 「いったい何があったんだ!?」 Aの声に気付いてJは、シルクハットを傾けテラスに顔を上げた。「事故のようだね。可哀想にすでに死んじゃってるよ」 「死んでるだって!?」 驚きのままAはテラスを後にして、わき目もふらずに現場へ駆けつけた。 テラスの真下はエントランスを出てすぐの場所だ。つまり、外に出掛けるか、もしくは訪問者があった場合、嫌でも目につく場所。 Gは石床に仰向けで倒れていた。後頭部の辺りから血が出ているのか、頭は朱の海に沈んでいる。そして、顔はハンカチで隠されていた。 「このハンカチは?」 Aが尋ねるとすぐにJが返した。 「ボクが置いた物だよ、あまり良い死に顔とは言えなかったものでね」 果たしてどのような死相を浮かべているのか? 恐る恐るAはハンカチを捲り上げ、その形相を確認した。 「……っ!」 思わずたじろぐA。 いったい彼は死に際に何を見たと言うのだ。まるでそれは悪魔でも見たかのような醜悪な形相で死んでいた。 「なんでこんなことに……」Aは沈痛な表情で頭を抱えた。 「さあ、だいぶ酔っていたようだから、それで誤ってテラスから転落してしまったのだろうね」Jはそう言うが、この形相はどうやって説明するのだ? ほかにも少し疑問な点がAにはあった。 「発見したまま誰も動かしていないのですか?」 「ボクが第一発見者だけど、ハンカチを掛けただけでほかは一切いじっていないよ。それ以前のことは知らないけどね」 屍体を発見して、周りに知らせたのはJだったらしい。 うつ伏せではなく、仰向けの屍体。酔っていて落ちたのだとしたら、どのような格好で転落したと考えても不思議ではないのだが……。 「警察には知らせたのですか?」尋ねながらAは周りの人々を見回した。 「そんな必用がどこあって?」 マダム・ヴィー、そのルージュから発せられた言葉だった。 今日もその素顔を隠し、ただ一箇所――魅惑的な唇だけがこの世界に姿を見せている。 自ら日傘を差すマダム・ヴィーは、召使いに車椅子を押させ、すぐ屍体の近くまでやって来た。 「嗚呼、なんという悲劇。転落事故から奇跡の生還をしたというのに、まさか酔って身を滅ぼすとは……可哀想な〝事故〟」 まるで舞台女優のように、マダム・ヴィーは芝居がかった仕草と口調で悲しんで見せた。それがAには引っかかって仕方がなかった。 「しかし、事故だとしても警察に連絡する必用はあるのでは?」 「おほほほっ、人里を離れたこの屋敷まで、ただの事故で警察にご足労を掛けるなど申し訳ないわ。事を大事にする必用など、どこにもないのよ。わたくしが責任を持って手厚く埋葬いたしますわ」 「しかし、彼は僕の友人であって――」 Aの言葉を遮るようにJが割り込んできた。 「マダム・ヴィーがそうおっしゃるなら、すべてお任せしようじゃないか。ボクらは客人なのだから、面倒なことをする必用はないさ」 「…………」 押し黙ったAは孤独を感じた。Jがマダム・ヴィーの肩を持ったように感じたのだ。 やはり誰も信じることはできない。 言葉や行動などいくらでも偽れるのだ。だとするならば、Aはもう少しGの屍体を調べたかったのだが。 「さあ、早く屍体を片付けて頂戴」主人の命令によって、召使いたちが素早く屍体を運んで行ってしまった。そのときの口調は、まるで〝邪魔よ〟と言いたげなものに感じられた。 AはGの死に不信感を持っていた。決め手となる理由はないが、この屋敷でのことすべてが疑わしいのだ。故に、なにが起きても不信感を抱いてしまう。例え本当に事故死だったとしてもだ。 なにを信じていいのかわからない。その中で、Gの言葉が本当だったとするならば、Aの正体を知る人物を失ってしまったことになる。これは大きな痛手である。 Gの死というあまりの衝撃で、大事なことを忘れていたが、Aはあのことをマダム・ヴィーに問い詰めることにした。 「マダム・ヴィー、お尋ねしたいことがあるのですが?」 「なにかしら?」 「この仮面のことなのですが、なぜ皮膚に密着して外せないのですか?」沸き起こる感情を抑え、冷静に淡々と尋ねた。 マダム・ヴィーの口元が笑みを湛えた。 「外す必用などないわ」 「必用があるないではなくて、僕が聞いているのは、僕に断りもなく顔に仮面を貼り付けるなんて、酷いとは思わないのですか?」 「ご自分の立場を理解していて? 貴方は客人、この屋敷の主はこのわたくし。郷にいれば郷に従うのが礼儀でしょう。ご安心なさい、この屋敷から立ち去るときに外して差し上げるわ」 立ち去るとき……それはいつになるのか。このまま立ち去ってよいものだろうか。 Gは死に、Aの記憶も戻らない。果たしてAの取るべき行動とは? 「失礼しました。目が覚めたら突然この屋敷にいて、戸惑いや不安も多く、仮面が外れないことに驚いてしまい、このまま一生外せないのではないかと考えたら頭が混乱してしまって。そうです、友人の突然の死も心身ともに堪えているのでしょう。この屋敷の主であるマダム・ヴィーに物言いを付けるような真似をして、大変申し訳なのことをしてしまいました」 そして、Aはマダム・ヴィーの足下に跪き、深く頭を下げた。 今はこれでいいのだ。穏便に済ませて機会を狙う。何かを探るにしても、機嫌を損ねた相手の口は固く閉ざされてしまう。だから今は、そう、これでいいのだ。 マダム・ヴィーの口元は嘲笑を浮かべているようだった。 「そこまでなさらなくても宜しくてよ。この屋敷の主が誰であるか、それをご理解いただければ」そう言って車椅子を反転させ、「それではわたくしは失礼するわ。日差しの下は苦手なもので」 召使いに車椅子を押され、マダム・ヴィーは屋敷の中へと帰っていく。 すでに召使いたちが血痕に水をまいてブラシで削り取るように擦り取っている。玄関ということも考えれば、早急な処理が必用なのはわかるが、Aにしてみれば証拠までも消えていくような気がした。 Aとマダム・ヴィーのやり取りの一部始終を見ていたJは、「この屋敷に自らの意思で来る者たちは、マダムに対してキミのような口の利き方はしないだろうね、怖い怖い」 「逆らうとなにかありますか?」 その問いには答えず、JはGの屍体があった場所に顔を向け、すぐに再びAに顔を向けると、にやりと口角を上げた。 なにが言いたいのかは明らかだ。 しかし、それを示唆すると言うことは、JもGの死について……。 「ゆっくりと二人で話しませんか、Jさん?」 「キミから誘ってくれるなんて嬉しいね。しかし、残念だなぁ、急ぎの用があるんだ」 「急ぎの用?」 「いやいや、たいしたことはないさ。それでは失礼するよ」 ステッキを手にしたJは優雅な足取りでこの場を去っていった。 急ぎの用とはいったい何か? シルクハットを被り、ステッキを持つ姿は、出掛ける装いだったからだろう。自然な流れを想像するならば、出掛ける身支度を済ませて屋敷を出たところで、Gの屍体を発見したと考えるのが筋の通る考えだ。急ぎの用と言えど、屍体を発見してしまっては足止めをされたのだろう。 しかし、この考えは〝急用の理由〟に繋がるものではない。 理由には繋がらないが、この考えが重要であるとAは考えていた。なぜならばAはしかと、その眼で見たのだ――Jが屋敷の中に入って行ったのを。 酔って転落をしたのならば、その前提すらも偽りである可能性もあるが、もしも酔いも覚めぬ夜に転落したとするならば、玄関を〝出る〟ときにしか通常では屍体を発見することはないのだ。つまりそれが意味することは、Jが屋敷の中に入っていったのは、やはり不自然とであるということだ。 たしかにJは出掛けようとしてたのだろう。だが、それは急用ではないかもしれない。中に入っていった行為、それが急用なのだ。その仮定を建てるならば、出掛ける予定が妨げられた点から急用だと言い出すまでの点の間、そこで〝急用〟が生まれたことになる。 直感的にAは〝急用〟とはGの死に関係することだ感じた。 すべては仮定の話である。 証言ではなく物証を見つけ出さなくては真実は見えてこない。 AはJを探そうと屋敷の中へ戻った。 夢の館専用掲示板【別窓】 |
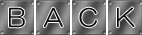
| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第4章「死の舞踏」 | ▲ページトップ |