| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第6章「闇からの呻き声」 | ノベルトップ |
| 第6章 闇からの呻き声 |
屋敷で意識を取り戻して、まだ二日。知らぬ場所の方が多い。屋内ではなく、屋外の庭となればなおさらのこと。 Aは玄関を出て庭の散策をすることにした。 玄関にはすでに人ひとりいなかった。そこに残っていたのは清掃で撒かれた水の跡。証拠などまったく残っていそうもない。 早々にその場からAは移動することにした。 広い屋敷だが、その庭はさらに広い。玄関から遠く先に塀が見て、そこをなぞるように視線を動かすと、巨大な門が見えた。どうやら門は固く閉ざされているようだ。 玄関正面から門までの道は庭園と呼ぶに相応しく、噴水から迸る飛沫が水路へ流れ続いている。そして、目に飛び込んでくる一面の紅い花。 風に運ばれてくる花の香りは甘美で、少し意識が遠くなるような気がする。 Aは早足で歩きながら巨大な門までやってきた。 近くで見る巨大な門は圧倒的であった。その大きさは五メートル以上。重厚感のあるその金属製の門には、禍々しい装飾が施されており、よく見るとそれは悪魔や悪鬼を模った物だった。 門にはこちら側に左右に二つの鍵穴があった。 Aは冷たい門に両手を押し当て押してみたがびくともしない。さらに肩を押しつけて、全体重をかけてみたが結果は同じ。鍵が掛かっているのか、掛かっていなかったとしても、この見るからに重い門はひとりの力では到底開かないだろう。 諦めてAは塀に沿って歩き出した。 塀の高さは門と同様、よじ登ることなどできない。さらに塀の上にはかぎ爪のような鉄柵が取り付けられている。しかも、そのかぎ爪は外ではなく、内に向かっているではないか。それの意味することは容易に察しがつく。 Aは苛立ちを覚えながら塀に沿って歩いた。 どこまでも続く塀。 やがて屋敷の裏までやって来たところで、異臭が鼻を突いた。 花が咲いていた。 それは表の庭に咲いていたものとは違う、どこか妖しげな紅い花。 花を咲かせているものはまばらで、その多くは不気味な実をつけていた。 茎の先端に実る卵のようなそれはおそらく「この実は……ケシ畑か」。 ケシの実から抽出される乳液はアヘンの材料となる。そのアヘンからモルヒネ、さらにはヘロインが生成される。 Aは袖で鼻を覆いながらその場を足早に立ち去った。 そして、庭の隅に見えてきた焼却炉。 焼却炉はまだ何かを燃やしているらしく、煙突から舞い上がった灰がAの足下まで落ちてきた。 さらに焼却炉の周りを調べて見ると、少し焦げた布の切れ端が見つかった。その布にはボタンがついており、服か何かではないかと思われた。 「まさか……」とAは呟き、嫌な予感を脳裏に過ぎらせたが、その考えはすぐに掻き消した。 煙の臭いに変わった点はない。肉を焦がしたような異臭はしなかった。 人の気配がする。Aはすぐさま苗木の陰に身を潜めた。 巨漢の男が巨大な麻袋を担いでこちらにやって来る。 近くまでやって来たその大男の顔は死人のように青白く、目の下の隈やいたることにある皺が疲弊感を醸しだし、額を横に走る手術跡が不気味だった。 大男はAに気づかずに横を通り過ぎ、さらに先にある井戸らしき場所で足を止めた。そして、麻袋の中身を井戸の中へ放り投げた。 思わずAは息を飲んだ。 一瞬見えたあれは、たしかに人のようであった。麻袋に入っていたのは人だ。それが今目の前で、井戸の中へ投げ捨てられたのだ。 しばらくして大男が姿を消したのち、Aは恐る恐る井戸に近づいた。 一見してそれは井戸のように見えるが、その直径は通常の井戸よりも遙かに大きい。まるでそれは地獄に続く大穴。底は暗闇に呑み込まれてしまっている。 焼却炉では脳裏を過ぎった考えをすぐに掻き消したが、ここではどうしてもそれが消えない。 投げ込まれた人は誰だったのか? 遠く離れていた為、それを確認することはできなかった。もしかしたら人ではなく、ただの人形だったかもしれない。 Aは荒くなる呼吸を落ち着かせながら、井戸の縁に手を掛けて中を覗き込んだ。 どこまで続いているのか、光すら届かない井戸の底。 急にAは背筋を冷たくして体を強ばらせた。 呻き声。 微かに呻き声が聞こえたような気がした。 もしも投げ込まれたのが……だったとして、死者の呻き声が聞こえたとでも言うのか。それとも別の者の声か? 「誰かいるのか!」 井戸の底に向かって叫ぶが返事は返ってこなかった。 呻き声に聞こえたものは風の悪戯だったのか。 Aは逃げ出した。この場所に一秒たりとも居たいとは思わなかった。 冷や汗をかきながら屋敷の中へ戻ってきたが、この中ですら居たいとは思わない。 今はこの場所が魔の巣窟に思えてならない。 いったいこの屋敷で何が起きているのか? 記憶を失い目覚めた場所は異質な決まり事で縛られた屋敷。その屋敷でお館様と呼ばれる謎の女主人マダム・ヴィー。取り巻く異質な奴隷たち、そして癖のある客人たち。 一刻も早くこの屋敷からAは出たいと願ったが、それをマダム・ヴィーに申し出たところで、容易に受け入れられるだろうか。おそらくそう簡単にはいかないだろう。 屋敷の中へ戻ってきたAだったが、やはり中にいることも躊躇われ、またすぐに外へ飛び出してしまった。 玄関を出てすぐの場所に残っていた水跡も、すでに跡形もなく消えてしまっていた。 Gの持ち物も処分され、その遺体も今はどこにあるかわからない。この屋敷からGの痕跡が消え、まるでいなかったことにされてしまうような。Aはそのことを考えながら恐怖を覚えた――自分もいつかは消されてしまうのではないかと。 この場所から逃げ出す方法を模索する。 門からの脱出は難しいだろう。鍵を手に入れたとしても、やはりあの重さが問題になる。 塀は高く、その上にはかぎ爪の柵が取り付けられているが、梯子があれば越えられないこともないだろう。梯子の一つくらい屋敷のどこかにありそうだ。 物置のような場所が屋敷の部屋の一つにあるか、それとも庭に小屋があっただろうか。 先ほどまで庭を散策していたAだったが、塀に沿って半周ほどしただけで、引き返してしまった。まだ広大な庭に何があるか把握していない。 Aは屋敷にある部屋を思い出した。 今のところ把握している場所は、いくつかの客間と、食堂とサロン。おそらく半分にも満たないほどしか行っていない。マダム・ヴィーの部屋すらどこにあるのか知らない。 マダム・ヴィーの部屋はどこにあるのか。 車椅子であることを考えると一階にあるような気もするが、それらしき部屋は今のところ見当たらなかった。二階もAの部屋は角部屋であり、テラスや階段を挟んだ向こう側にはまだ足を運んでいない。 そして、前々から言われていた地下室の存在。 地下室には不用意に近づかないようにとの旨を伝えられているが、地下に降りる階段がどこにあっただろうか。 Aは考えを廻らせながら屋敷の全容を眺めた。 玄関をすぐ出た場所からでは、首を大きく動かなければ眺めることはできない。 屋敷を眺めながらAは足を運んだ。 そして、ふと一階の窓へ目をやったとき、カーテンの隙間からこちらを見る人影に気づいた。 人影が誰かははっきりしない。ただ、あの部屋は確か……Mの部屋だ。そのことに気づいたAはすぐさま部屋の中へ引き返し、Mの部屋へと急いだ。 まだ会ったことのないMと呼ばれる女性。 部屋の前に立ちAは扉を力強く叩いた。反応はない。これは前に来たときと同じだ。 しかし、今は部屋の中に何者かがいるに違いなかった。 Aは激しく扉を叩いた。 「部屋の中にいることはわかっています。顔を見せてはくれませんか!」 もしかしたら入れ違いになったことも考えられなくもないが、Aはここまで極力急いで来たし、すれ違った人も誰ひとりとてしなかった。 さらにAは強く扉を叩いた。このまま扉を壊してでも中に入るような気迫だった。 「M女史、貴女に人目お会いしたい。ご存じかもしれませんが、昨日まで僕は意識を失いこの屋敷の一室で寝ておりました。昨日やっと目を覚まし、ほかの客人にはお目通りしたが、貴女にはまだお会いできておりません!」 扉越しに言葉を投げかけるが反応はなかった。 仕方がなくAは諦めて引き返そうとしていた時に、扉の鍵が開く音がした。 すぐさまAは振り返って扉の前に立った。 すると、少し開かれた扉の隙間から、蒼いベールに包まれた目元が覗いた。 「何かわたくしにご用ですか?」 落ち着いた、まるで小川のせせらぎのように澄んだ声音。 先ほどまで何かに駆り立てられていたAだったが、急に落ち着きが戻ってきた。 「僕はこの屋敷ではAと呼ばれています。貴女がM女史でしょうか?」 少し答えるまでに間があった、「ええ、このお屋敷ではそう呼ばれておりますわ」 いざ会って見るとAは何を話していいのかわからなかった。会うことばかりに執着していた。 「少しお話があるのですが、Gが亡くなったのはご存じですか?」 その問いを聞いて、ベールの奥の瞳が大きく見開かれた。「いえ、今初めて……部屋からあまり出ないもので、人との会話も日に二言三言、世話係の者とするくらいなものですから」 部屋から出ないということは、先ほど訪れた時には居留守を使われたのか。 そこのことよりも、人が死んだというのに誰も伝えに来ないとは……来たのかもしれない。その時も居留守を使った可能性がある。 Mは警戒しているのか、未だに扉は少しだけ開き、そこから顔を出している状態だ。会話が途絶えたらすぐにでも扉が閉まりそうな雰囲気さえある。 「Gはテラスから転落して死んだようです。それについて何かご存じではありませんか?」 「先ほども申したとおり、今初めて聞いた話ですので」 「では今までGとどのような会話をしましたか、たとえば僕のことなど聞いていませんでしたか?」 「いいえ、Gさんとは挨拶を交わした程度ですので。なに分、部屋の中にいることが多いもので」 この屋敷に何度も訪れたことのあるJですら、あまり会話をしたことがないと言っていたほどだ。 Aは会話が途切れないようにすぐに新たな質問をする。 「つかぬ事をお伺いしますが、なぜ部屋に籠もりきりなのですか?」 「それは……あまり体が強くないもので。人を接することも苦手ですの」 蒼いベールで隠された素顔。目元を見る限りでは不健康そうには見えないが、それ以上のことは伺い知れない。 ほかの質問はないかとAがほんの少し考えている間に、Mのほうから口を開いた。 「もう宜しいですか?」 扉が少し閉まりかけていた。 慌ててAは、「この屋敷に長く滞在していると聞きました。なぜですか?」 その問いかけにMは答えなかった。 しかし、「お入りなさい」と扉を大きく開いたのだ。 導かれた部屋の作りはAやGの部屋とあまり変わらない。違う場所と言えば、本棚とそこに納められた大量の本だろうか。 「お掛けになって」MはAに席を勧めた。 Aが腰掛けた椅子の前には小さな丸テーブル。その上にはしおりの挟まれた読みかけの本と、飲みかけの紅茶。 Mは持って来た新たなカップに紅茶を注ぎAに差し出すと、自分も席に着いた。 蒼いベールで素顔を隠し、全身も同じような布で隠されている。まるでそれはイスラム教の女性のような隠しようである。紅茶を注いだときの手ですら手袋で隠されていた。 Aは「なぜ部屋に入れてくれたのですか?」と不思議そうに尋ねた。 「この屋敷には至る所に〝眼〟がありますのよ」 「それは監視の眼ということでしょうか?」 思い当たる節がある。サロンでJと会話をしていた時のことだ。気づいたら二号の視線、そして現れたマダム・ヴィー。 「監視……マダム・ヴィーが奴隷たちにわたくしたちを監視するように命令しているとでも?」 「違いますか?」 「違わないとは言えませんけれど、この屋敷には別の者の〝眼〟もありますのよ」 「誰の眼ですか?」 「たくさんの〝眼〟。マスクで覆われたたくさんの〝眼〟たち。部屋の外で話していれば、必ず誰かの〝眼〟に止まります」 果たして誰の眼に止まるというか。マダム・ヴィーや奴隷たちの眼でないとしたら、客人たちか、それともまだAの知らぬ者たちがいるのか。 誰の眼であれ、この屋敷にいる者たちは信用ならない。Mは今、Aに忠告めいたことを話しているが、その意図ですらどこにあるのかわからない。 部屋に招き入れたと言うことは、その〝眼〟に聞かれたくない話がある筈。 乾きはじめた喉をAは紅茶で潤した。 「もしかして僕に何か大事な話でもあるのですか?」 「…………」しばらく黙したのち、「この屋敷からお逃げになって。貴方はこの屋敷にいる誰とも違う。招かれざる客は早々に屋敷を立つべきですわ」 「逃げる? 穏やかな話ではありませんね。この屋敷にいると僕に何か大変なことが起こりますか?」 Aの脳裏に過ぎったのはGの死。 「何が起こるのか、それは起きてみないとわかりませんわ。ただ……マダム・ヴィーは気まぐれなお人ですから」 「それはマダム・ヴィーが僕に何かするということですか?」 「ええ、すでに。わたくしは貴方に注意を促すことはできても、手助けをすることはできません。むしろ、その逆でしょう」 「逆?」 「この部屋には貴方とわたくし、そしてほかの者の〝眼〟が実はあるのです。その者は実に気まぐれですから、もしかしたら貴方の邪魔をすることになるかもしれませんわね」 「誰かにいるのかこの部屋に!」 「どちらの手に委ねるか……そう考えた時に何を優先するべきか。貴方が客人ということをお忘れなく、客人であるうちは安全ですわ。少なくともマダム・ヴィーの魔の手からは……」 「教えてくれ、マダム・ヴィーのほかに……危険な……」Aの眼が見開かれた。「飲み物に何か……どうして……貴女が……」 Aの意識は深い闇に呑まれた。 夢の館専用掲示板【別窓】 |
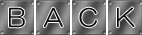
| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第6章「闇からの呻き声」 | ▲ページトップ |