| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第12章「深紅の魔獣」 | ノベルトップ |
| 第12章 深紅の魔獣 |
「ご機嫌ようマダム・ヴィー。こんな陰気くさいところで貴女にお会いするとは、不釣り合いな場所だね。それとも此処こそが貴女の城かな?」 「J……どうして貴方が……」 驚き言葉に詰まるマダム・ヴィー。 「さて、どうしてだろうね」 人をからかうような口ぶりのJ。 血塗られた鋸を見れば、芳しくない状況であることはわかる。ただ、マダム・ヴィーはなぜJがそのような真似をしたのか、わからない様子だった。 「貴方の目的は何なのかしら……わたくしを快く思わない人間の一人だったというわけ? 今までわたくしを騙し続けていたというの!」 マダム・ヴィーの叫びが木霊した。 笑みを浮かべたJの唇。これほどまで邪悪な笑みは見たことがない。 「貴女はボクのことなど覚えていないかも知れない」Jは車椅子のマダム・ヴィーに躙り寄った。 この時、Aの躰は徐々に回復しつつあり、微かに動いた首を横に曲げそれを見た。 JはAに背を向けた形で、マダム・ヴィーの目の前で仮面を外したのだ。 「でもね、この顔の傷は貴女のことを覚えている。そして、この斬られた片足もだ」 言い放ったJの肩越しに見えたルージュが驚き開かれた。 「あの老いぼれの……子供の……若くて最も美しい顔を持つ……そんな嘘よ、魂のない家畜と化した貴方が!」 「地獄から蘇ったと言うべきか、ボクは今此処にいる」 「何が目的、何が目的なの!」 「貴方の夢の終わりを告げることだよ」 「わたくしを殺す気!」 「そんな生ぬるい真似はしないよ。キミは生かす、現実の中でね」 突然、奇声をあげたマダム・ヴィーがJに襲い掛かった。だが、マダム・ヴィーは非力な女でしかなかった。この場には奴隷たちもいない。マダム・ヴィーはJに車椅子から引きずり落とされてしまった。 さらにJは車椅子を遠くの壁に投げつけた。 「ちょうどいい、この部屋には貴女を拘束する手錠や鎖がいくらでもある」 Jはマダム・ヴィーに背を向け、壁に掛かっていた拘束具を取ろうとしていた。そんなJの脚を床で這っていたマダム・ヴィーが払った松葉杖に取られてしまい、思わず転倒を余儀なくされた。 すぐにマダム・ヴィーはJの躰に飛び掛かった。 真っ赤に燃えるルージュが牙を剥く。 Jの瞳孔が開かれた。 まさか、そんなことが起ころうとは――マダム・ヴィーがJの首に噛み付こうとは思い寄らなかった。 頸動脈は歯によって引き千切られ、噴き出した血はマダム・ヴィーのベールとルージュをさらに紅くした。 痙攣をするJに馬乗りになりながらマダム・ヴィーは嗤った。 「キャハハハハハッ、家畜の分際で、所詮は喰う者と喰われる者の違いなのよ!」 狂気の沙汰。 まだAは動くことができなかった。 マダム・ヴィーが床を這ってAに近付いてくる。その手がAの躰に伸びた時、部屋に二人の人間が飛び込んできた。 絶叫するマダム・ヴィー。 「M!」 そう、この場に姿を見せたのはM。さらにその横にはなぜか二号の姿が。 すぐにMと二号はAを抱きかかえて部屋から逃げ出すとする。 床に這いつくばりながら手を伸ばすマダム・ヴィー。 「おのれー、おのれーッ!」 叫び声をあげる真っ赤なルージュと、朱い死に化粧をしたJを残して、Aはこの場から逃げ出した。 松葉杖を突く音が追ってくる。だが、それも徐々に遠ざかって行った。 上へと続く階段。決して短い物ではないが、今は必要以上に長く感じられる。 二人に肩を借りて階段を登り切ったA。その躰はまだ言う事を聞かない。支えられて立っているのが精一杯だった。 地下を抜け出す扉の前にやっと辿り着き、二号が扉を開けた瞬間、熱風が地下に流れ込んだ。 屋敷に戻って来たAは愕然とした。 燃えていた。伏魔殿に相応しい地獄の業火が屋敷を包み込んでいたのだ。 すぐに玄関に向かったが、扉には鍵が掛けられていた。 屋敷中を駆け回る奴隷たち。逃げ惑いながらも、その忠義――いや、マダム・ヴィーへの恐怖を忘れていなかった。Mを見るや拘束しようと飛び掛かって来たのだ。 それを庇ったのは二号だった。 同じ奴隷同士で、二号もまたマダム・ヴィーを恐れていた。それなのになぜ、今になってマダム・ヴィーを裏切るような真似をするのか。 「お逃げくださいM様」 目の前の奴隷を押さえながら、切羽詰まる言葉であったが、Mはそれを聞こうとはしなかった。 「逃げるのなら皆一緒に」 そうしているうちに、やがてマダム・ヴィーが追い着いて来た。 「屋敷に火を放ったのは誰! 早く消しなさい、消すのよ!」奴隷たちに命令をし、Aに肩を貸すMの前まで一歩一歩と近付いて来る。「火を放ったのは貴女たちね!」 Mは何も答えずマダム・ヴィーと対峙した。 その場に新たに現れた奴隷がマダム・ヴィーに駆け寄って来た。「大変で御座います、奴隷の一人が台所を故意に爆発させたようです」 さらに別の方角から駆け寄って来た奴隷が、「屋敷の至る所から炎が上がっております。もうこの屋敷は……」 叱咤するマダム・ヴィー。「うるさい! 何があろうと消すのよ、この屋敷を守るのよ!」 この間にも炎は屋敷を蝕んでいた。 Aは急な目眩に襲われた。激しい頭痛の先に、何かが見えようとしていた。そうだ、この頭痛と目眩は、何か思い出せそうになった時、それを妨げるもの。 紅玉が艶やかに燦然と耀くよう、華やかな舞踏会は紅く燃え上がった。 火を放ったのは――。 「お前だ!」 叫んだAが指差したのはマダム・ヴィー。 突然のことにマダム・ヴィーは何を言われたのか理解できない様子だ。 Aは言葉を続けた。 「あの夜、お前は屋敷に火を放った。そして、そして……」 よく思い出せない。 遠い過去から聞こえる鋸を引くような悲鳴。背の高い紳士が突然に藻掻き苦しみ、果てに狂い理性を失い淑女に襲い掛かった。それは何の記憶か? 「そして、我が夫に毒を盛ったのです」とMが静かに言った。「狂乱した夫は人々を襲いました」 Aの記憶が少しずつ穴を埋めていく。 真っ赤なルージュが嗤っている。あの時、この時も、あの艶やかな唇は人の命を弄びながら笑みを浮かべる――マダム・ヴィー。 「復讐のつもり? 何を今さら」マダム・ヴィーはMを嘲笑い、「貴女も十分愉しんだでしょう――Sとして」 「この環境に十能するために生まれたもう一人のわたくし。彼女がどんなに抵抗しようと、もう終わらせなくてはならないのです」 「そうね、仕方がないわね。終わらせてあげるわ、Mを殺すのよ、殺しなさい、S諸共死ね!」 奴隷がMに襲い掛かる。 まだAは思うように動けない。 突如現れた黒い壁。 MとAの目の前に背を向けて立つ大男が、持っていた灯油缶で奴隷を殴り飛ばした。 それを見たマダム・ヴィーが叫ぶ。 「なぜ、生きた屍と化した貴様がなぜ! 記憶など疾うに無い人形の分際で!」 その問いにMが答えを出す。 「姿形を変えられようとも、例え記憶を消されようとも、ひとは魂を持っているのですよ」 そして、奴隷たちはマダム・ヴィーの命令を聞くことを止めた。 屋敷の崩壊と共に、その支配も終わりを告げようとしていた。 奴隷たちが逃げ出しはじめた。 出口である玄関の扉に群がる奴隷たち。その頑丈な扉は囚われた人々を逃がしはしない。おそらく鍵を持っているのはマダム・ヴィー。この状況下に置いても、マダム・ヴィーに襲い掛かろうと考える奴隷はいなかった。 しかし、Aは奴隷ではなかった。 「玄関の鍵を開けろ!」 「わたくしに命令する気? 誰もこの屋敷からは逃がさないわよ!」 窓は全て嵌め殺し。さらに窓には鉄枠が格子に取り付けられており、硝子を割っても人が通り抜けることは出来ない。勝手口のあった台所はすでに爆発で倒壊しているだろうし、その場所に行くにしても廊下はすでに火の海だった。 もうこの場所も時間の問題だ。 マダム・ヴィーから鍵を奪わなくてはいけない。それが解っていても、長年の呪縛から逃れられず、躰が竦んでしまう。奴隷たちも、Mも、躰が震えている。 渾身から力を振り絞り、Aが自由の利かない躰に鞭を打ち床を蹴った。 「鍵を開けろ!」 燃え上がる大階段を背にして、悪魔が嗤った。 飛び掛かって来たAに隠し持っていた短剣の切っ先を向けたマダム・ヴィー。 躰の自由も利かず、さらに勢いのついてしまっていたAは、その刃を避けることができない。 まるで引き寄せられるようにAの躰は妖しく煌めく切っ先へ。 その時だった! 大男がAの躰を突き飛ばし、自らがその刃の餌食に――。 腹を刺された大男は表情ひとつ変えず、マダム・ヴィーの躰を振り払った。 その時のマダム・ヴィーの驚愕したルージュ。 松葉杖を放り出し床に倒れたマダム・ヴィーから、鍵の束が放り出された。 急いでAは鍵を拾い上げ、立ち上がろうとした時、なぜか大男に激しく突き飛ばされた。 何が起きたのかわからずAが大男を見つめ、それに気づき叫ぶ。 「父さん!」 記憶が戻った瞬間、崩れ落ちた天井から巨大なシャンデリアが降って来た。 その真下には大男と、そしてマダム・ヴィー。 「ギャァァァァァッ!」 絶叫。 地獄から聞こえて来たような紅い断末魔。 床に叩きつけられたシャンデリアから硝子片が飛散する。 思わずMは目を背けた。 「なんてこと……」 燃え上がるシャンデリア。 二号はAに肩を貸し、さらにMの手も引いた。 「行きましょう」 その言葉は淡々としながらも、Mの手を握る手には力が入っていた。 群がっていた奴隷たちが道を開け、玄関の前までやって来たAは、手に入れた鍵の束を一つ一つ試し、ついにその扉を開けた。 奴隷たちが玄関の外へ流れ出す。 屋敷が燃える。一刻も早くこの場を離れなくては危険だが、離れたい理由はそれだけではない。屋敷からだけでなく、この敷地内から一刻も早く離れたい。 庭の先にある正門を越えてはじめて、自由が得られるのだ。 鍵を持っているのはAだが、奴隷たちは我先にとAたちを抜かして正門へ向かう。 AとMと二号。三人は並んでゆっくりと歩み出す。二号はAに肩を貸し、さらにMの手を引き、三人を結びつけながら。 魔獣の嗤い声が背後から聞こえた。 全身を地獄の炎に包まれた深紅の魔獣。 牙を短剣に持ち替え、三つ足の魔獣が三人に襲い掛かる。 いち早く気づいたのはMだった。 目についた者を狙ったのか、それともはじめから彼女を狙ったのか、魔獣は二号に襲い掛かった。 それをさせまいとMが立ちはだかる。 惨劇は繰り返される。 二号を庇ったMは脇腹を刺され、その姿はAを庇った大男――父に重なった。 Mは魔獣を強く抱きしめた。 蒼い夜がまるで紅い夕焼けを包み込むように、二つの影絵は交わった。 いや、交わったのは、三つの影だったのだろう。 灰が空に舞い上がる。 母は言った。『いきなさい』――と。 崩れ落ちた時間と影。 声すら出せずAはその場から動けなくなった。 それでも二号はAの手を引いた。 「いきましょう」 二号に導かれAは正門へ向かう。 そこにはすでに奴隷たちが扉が開くことを切に願って待っている。 Aは悟った。 この扉を開かなくてはいけないのは自分だと。 それが宿命なのだと。 鍵の束にある一段と大きな鍵。その鍵は天使の浮彫で模られていた。この鍵が地獄を模った門を開ける物だと直感を覚えた。 天使の鍵を鍵穴に差し込む。 奴隷たちは静まり返っていた。 回される鍵。 響き渡った鍵の開く音。 嗚呼、ついに外への扉が開かれる。 門を開けた奴隷たちだったが、誰一人として外に出ようとしなかった。彼が外に出るのを待っているのだ。その権利を与えられたのはA。 Aは二号に肩を借りながら門の外に出ようとした。その時に気づいた門の外側の模様。皮肉なことに天使たちが戯れる模様だった。 屋敷の内側から見る正門は地獄、屋敷の外から見る正門は天国。 実際は天国の門をくぐった先にあったのは地獄だったと言うのに。 そして、Aは自由の大地に立った。 目の前に広がる青々とした緑。 森を切り開いた小道がどこまでも続いている。 この道は果たしてどこに続いているのか? 寄り添って歩き出すAと二号。 すぐに前方から馬に乗った男がやって来た。その男はAの前で馬を止め、蒼白な顔をしてAと前方で燃え上がる屋敷の影を交互に見た。 「いったい何があったんだ、マダム・ヴィーは無事なのか?」 その言葉でマダム・ヴィーの関係者だとすぐに知れた。 Aは答えなかった。 代わりに二号が答える。「お館様は自らの炎に焼かれお亡くなりになりました――最期まで夢に抱かれながら」 男は二号のフェイスマスクを怪訝そうに見ていた。 「マダム・ヴィーの奴隷か。それにしても、侯爵様が亡くなられた矢先だというのに、マダム・ヴィーまで……」 マダム・ヴィーの策略によって寝たきりにされた領主X。見知らぬ場所ですでに亡くなっていたのだ。それはマダム・ヴィーにどんな運命をもたらす筈だったのか。 「僕たちにはもう関係のないことだ」Aは呟き二号と向かい合った。「もうこの君のマスクはいらない」 Aは二号のマスクを外した。 そして、少女の素顔を見て大きく息を呑んだ。 夢の館専用掲示板【別窓】 |
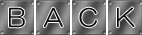
| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第12章「深紅の魔獣」 | ▲ページトップ |