| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第11章「煉獄迷宮」 | ノベルトップ |
| 第11章 煉獄迷宮 |
まだ陽の高いうちから二人は地下に足を踏み入れた。 細心の注意を払いJが洋燈に火と点ける。一瞬にして仄かに染まった長い階段。だが、その先はぽっかりと口を開けて闇へ手招いている。 再びこの道を下ることになるとは、Aは躊躇せずにいられなかった。それでも構いもせず先を進むJについて行かざるを得ない。もう後戻りができないことはAも重々承知していた。 Jは地下で何をしようとしているのか。彼の話によれば、この地下に外への出口があるらしいが、その話はついでに出てきたようなもの。おそらく彼の目的は別にある。 地下は空気は重く湿っている。そして、どこからから臭ってくる生臭さ。 獣の臭いのようだが、それは紛れもなく人の臭い。汗や肉、さらには血の臭いだ。 ついにあの曲がり角まで来た。道は二手に分かれている。 立ち止まったJ。「さて、どちらに進むべきか」振り返りながらAを見た。 「すぐあちらにある部屋でマダムは拷問をしていた」 「拷問ではなく調教だろう。では、逆の道を進んでみるとしよう」 廊下は果てなく続く。まるでそれは地獄へ続く洞窟のように。 やがて二人は鉄格子の前までやって来た。それは牢屋であった。狭い牢屋の先の暗がりで、何かが蠢いている。 微かに聞こえてくる呻き声。まるで地獄を吹く風のような低い声であった。 Jは恐れもせず洋燈を鉄格子の隙間から中へ入れ、暗がりを仄かに照らした。「誰か居るのか?」 返事と呼べるものは返っては来なかったが、獣が威嚇に発する唸り声のようなものが聞こえた。 Jは再び、「誰か居るのか? 奴隷か、それとも――男爵様でしょうか?」 その呼びかけに、牢屋の隅から何かが這って鉄格子に近づいて来た。 Aは一瞬、目を背けたがすぐにそれを凝視した。 果たして人と呼べるものなのか、乞食のような身なりをしたそれは、骨と皮だけの腕を突き出し鉄格子を握り締め、毛の塊と化した頭部の髪と髪の隙間から、鈍く輝く瞳でこちらを見ていた。さらに目を背けたくなった理由は、その者には両足がなかったのだ。着ている襤褸布で隠れているが、おそらくは脚の付け根あたりから消失している。 唸るような声で男は囁いた。「儂を知っておるのか?」嗄れた声であるが、芯は強く聞き取れる。 Jは恭しくお辞儀をした。「お初に御目にかかる。ボクが誰かおわかりか、男爵様?」 髪の隙間から覗く眼が大きく開かれる。何か思うことがあったのかしれないが、彼は押し黙って何も言わない。 薄く笑うJ。「御目にかかるのは初めてだが、ボクに何か思うところがあったみたいだね」そして、一呼吸置いて。「こうお呼びした方がボクの正体がわかるでしょう――叔父上」 「なっ!」男の短い一言に驚愕の度合いが込められている。 「隠し子の一人だよ、ボクの調べた限りではおそらく末っ子ということらしい」 「この伏魔殿に足を踏み入れるとは……ヴィーに正体を知られればただでは済まんぞ」 「もう過去に一度、ただでは済まなかったよ。けれど、マダムは今のボクが何者であるか気づいてはいないだろうね」 目の前で繰り広げられる会話にAはついて行けなかった。Jが地下に来た理由は、おそらくこの年齢もわからぬ男に会いに来ること。だが、それそのものが理由ではなく、先に何かがあるのだろう。 「口を挟んで悪いが、状況がよく掴めない」 Jと男の視線がAに向けられた。 なぜか楽しそうに笑っているJが、「ここにいるのは領主Xと呼ばれる者の弟だよ」 まさか! 以前、Jは領主Xの存在をマダム・ヴィーの夫として臭わせていた。そして、ここにいるのがその弟であり、叔父と呼ばれたと言うことは――。 「貴方は領主の息子なのか? そうだとしたら、マダム・ヴィーの息子でもあるのか!?」 声を荒立てたAをJは一笑した。 「とんでもない、ボクがマダムの息子だなんて。Xには何人もの愛人や、行き連りの女が山のようにいたのだよ。生ませた子供は数知れない。ボクもその一人に過ぎない――が、そのうち何人が生き残っているのか」 死んでいる……そう自然に何人も死ぬはずがないので、殺されたと捉えるべきだろうか。 「ボクはね、過去にマダムに捉えられ、奴隷として調教され、そして売られたのだよ。片足はその時に斬られた。それからボクは飼い主の元から逃げた――正確には飼い主は死んだのだけれどね」また楽しそうにJは笑った。 少しずつJの目的が見えてきたように思える。点と点が糸によって結ばれはじめる。 男はJに尋ねる。「兄御前はどうなったのだ?」 「さて、ボクは会ったことがないものでね。噂によれば生かさず殺さず、ずっと寝たきりだそうだ。おそらくマダムの仕業だろう、まだ彼女には実権がない、夫が死ねば自分の立場が危うくなることくらい承知なのだろう」 「貴君の目的は何だ?」 「マダムがなぜ叔父上をこの場所に幽閉したのか、外に出られては困るからだろうね。ならば外に出すのみだよ」 Jは懐から鍵を出した。古く錆びた鍵だ。それを見て驚いたのは男だ。 「どこでその鍵を……」 「ある男が大事に隠し持っていたよ。本人はその鍵が何であるか覚えていないようだけど」 「持っていただと? 疾うに死んだ男だぞ?」 「死んではない……いや、魂は死んでいると言うべきか。マダムに手を加えられたらしく、木偶の坊と化してはいるがね。A、キミも見たことはないかい、奴隷の中に大柄の男がいるだろう?」 大柄の男――その印象に当てはまるのは一人だ。額に大きな傷のある大男。たびたびAは危うい場面を目撃されている。 男は感慨深そうに瞳に何かを湛えていた。「そうか、生きておるのか。儂と同じく地下に閉じ込められておったが、儂と違い彼奴は死を選んだ。それでも死ねずマダムに活かされておるのか……惨い所業だ。正妻との間に生まれた子でありながら、一族と決別し女と駆け落ちして姿を晦ましたが、それでもヴィーの毒牙に掛かろうとは」 つまりあの大男は領主Xの息子と言うことになり、Jの義兄と言うことになるのだろう。大男の年齢は大凡だが中年かそれ以上、一方のJはまだ若いように思える。領主Xに多くの子がいるらしいが、子供たちの年齢の幅も大きそうだ。 複雑に絡み合う系譜。 Jは鍵穴に鍵を差して回そうとしたが、「回らないな。鍵が違うのか、それとも――」 「鍵穴が錆びてしまったのだろう」と男。 常にどこか妖しげな笑みを湛えていたJという男が、この時、苦虫を噛み潰したような表情を見せた。 「大丈夫だ、まだ時間はある。道具を探してこよう」Jは男に会釈をして身を返した。「では叔父上、またしばらくのちにお会いしましょう」 早足に去るJを追いかけて横についたAは「僕は貴方が何をしようとしているかわからないが関係のないことだ。ここで別れて出口を探すことにする」 「そうかい。キミにはキミの自由がある、ボクはキミの意志を尊重するよ」 Aは持ってきていた予備の洋燈に種火を貰い、二人は十字路で別れた。 地下はまるで迷宮のようであった。進めば進むほど道は入り組み、道を引き返すことも困難になりそうだ。 暗がりの奥から音が聞こえた。 幾つもの金属質のものが触れ合って響く音。 低い呻き声も聞こえてくる。それも一つ二つではなく、轟くように。 酷い獣の悪臭。 Aは洋燈を向けた。 牢屋の中で人間たちが蠢いている。また別の牢屋の中では、死んでいるのか生きているのか、まったく動かない人の群れ。そして、また別の牢屋の中からはこちらに手を延ばす少年の姿。 「助けてくれ!」 Aはどうするべきかわからず、思わず眼を背けた。 そして、逃げたのだ。 Aの背中に突き刺さる叫び声。足を速め逃げ惑う。地下に一秒たりとも居たくはない。それでも出口を見つけなくてはならない。 無我夢中で逃げたAは道を失ってしまった。自分がどの道を通ったのかわからない。このままでは屋敷にすら戻れない。 焦る気持ち。静かな地下に響く心臓の鼓動。荒い息づかい。 前方から明かりが近づいて来た。はじめはJかと思ったが、それが別の人物であると知ってAは慌てて自分の洋燈を消した。 暗闇に包まれながらその場から逃げようとした。だが、足下が覚束ず、思うように進めない。壁に手を添えながら歩くが、すぐ後ろからは明かりが迫ってくる。 このままでは逃げ切れないと思ったAは走ろうとしたが、躓き転倒してしまった。 手が擦り切れた。だがそんなことに構ってはいられない。後ろから迫ってくる車輪の回る音。 Aは起き上がり様に振り返った。 仄かな明かりの中でもそのルージュは燃えていた。 「こんな場所で何をしているのかしら?」 悪戯に妖しげな美声。 マダム・ヴィーは横にいた女奴隷に命じる。「弱い薬を打ってあげて」 フェイスマスクで覆われた黒い顔が徐々に迫ってくる。 Aは逃げようとするが、手は床を掻き毟り、腰が抜けて立ち上がれない。 奴隷は注射器を持っていた。 抵抗しようとAは手を振り上げたが、その手は易々と掴まれ、女とは思えない力で制されてしまった。 首に突き刺さる細い針。 すぐにAの全身から力が抜けた。まるでそれが自分の躰ではないように、まったく微動にしない。見開かれた瞳に映る真っ赤なルージュ。 「調教部屋まで運んで頂戴」 命令された奴隷はAの両脇に後ろから腕を入れ抱え込み、そのまま引きずって歩きはじめた。 引きずられながらも躰の感覚はなく、前を進んでいるのか、それとも立ち止まっているのか、Aの視界に映っていたのは長く暗い廊下。 突然、Aの視界は大きく揺れ、その躰は仰向けにされた。 部屋に備え付けてあった洋燈に火が灯される。 急な明かりにAは目を瞑りたかったが、瞬きすらも自由にできなかった。 天を仰いでいるAの耳に届くマダム・ヴィーの声。 「さあ、どうしようかしら。また記憶を消すか、それとも……」 失われたAの記憶。それはマダム・ヴィーによって故意に消されたものだったのだ。 マダム・ヴィーの繊手がAの頬を撫でる。 「奴隷にするか、生きた屍に改造するか、標本にするのもいいわ。憎いほどに完璧な肉体、夢を見る余地すら与えない肉体、どれ一つとて欠けてはいけない肉体。今まで何人もの少年の躰を切断し、わたくしが夢想の中に見ていた躰がここにある。少年の見えない腕はここにあった、脚も体も頭部さえ、やはり奴隷にはでない、完璧すぎるもの」 マダム・ヴィーの手がAの服を脱がしはじめる。すでにボタンが外れ、はだけていたシャツをめくり、その胸板に指先が這う。絵を描くように、音を奏でるように、マダム・ヴィーの指は躍った。 「けれど、この肉体が老いる様を見てはいられない。やはりこの躰をありのまま保存して眠らせるほかないのかしら。でも、でもそれでは動く姿が見られなくなってしまう。躍動する筋肉のうねり……動く様をまたわたくしは夢見なくてならなくなるわ。もどかしい、もどかしい躰だわ」 熱っぽい声が響いた。 「どうするべきか……不老不死の妙薬さえ……あら?」 何かに気づいたマダム・ヴィー。それを確認するために壁を見つめているようだった。 「道具が足りないわ」 マダム・ヴィーに顔を向けられた奴隷は慌てた様子で大きく首を横に振った。 「ぞ、存じ上げません。手入れをした道具を昨晩ここに戻した際には何一つなくなっておりませんでした」 「何が無くなっているのかしら?」 「鋸、それに金槌も無くなっております」 「貴方は知っているかしら、それらがどこに行ったのか?」 ベールに隠されたマダム・ヴィーがAの顔を覗き込んだ。 この状況で疑われるのはAだろう。現にAは地下に忍び込んでいた。まだマダム・ヴィーはJの存在に気づいていない。 思案している様子のマダム・ヴィー。 「貴方はこの地下で何をしていたの? そして、鋸や金槌を何に使おうとしていたのかしら……扉や牢を破るため、外へ逃げ出す為かしら。だとしても道具は今どこにあるの?」 マダム・ヴィーはAの下半身をまさぐりながら、ズボンの衣嚢から地下室の鍵を取り出した。 「この鍵で地下に潜り込んだのね。でも、どこでこの鍵を手に入れた……まさか、あの女。すぐにMを探しなさい! 屋敷の中だけではなく、地下も隈無くよ!」 奴隷の一人が足音を立てながら一目散に部屋を飛び出して行った。 マダム・ヴィーのルージュが歪んでいる。不快さを表していることは明らかだ。 「あの女、貴方が誰であるか気づいて情が湧いたのね。貴方をこの屋敷に残しておくためには、あの女を消す必要がありそうね。残念だわ、あの女にもう苦しみを与えることができなくなってしまうなんて」 嗤ったはマダム・ヴィーは、いつもの艶やかなルージュを取り戻していた。 そして、再び繊手でAの躰を撫でる。 「まだ老いるまでには猶予があるわ。一先ずは記憶を消しておきましょう。薬を持ってきて頂戴」 残されていたあと一人の奴隷もこの部屋から消えた。部屋に残っているのはマダム・ヴィーとAのみ。 「貴方をどうするか最終的に決定するまで、どうしようかしら。記憶を消したのちに、洗脳して、あの男の後継者にするのも良いわね。さすがにあの老いぼれを活かしておくのも飽き飽きだわ。ほかの跡取りは居ないも同然だものね。そこへ本当の孫が現れたら……」 Aは驚いたが、声すらも出せなかった。 マダム・ヴィーの言葉を解釈するのは容易いが、その事実を受け止めることは容易ではない。 本当の孫とは、Aのことで間違えないのか。躰の自由が利かな今、聴覚さえも冒され、聞き間違えだったのかしれない。 しかし、マダムは「これからは貴方が侯爵領を相続するのよ。爵位は貴方の物、そしてわたくしは貴方の妻に」 領主X――つまり領土を持つ存在。それが侯爵というわけだ。Aが領主Xの孫であることは間違いなさそうである。少なくともマダム・ヴィーはそう思っているのだ。 血塗られた系譜。 Aもまたその系譜に名を連ねる者であったのだ。 マダム・ヴィーに問い質したいことが山のようにあるが、今のAにはそれすらも適わない。 今この時もJは何かをしているだろう。そのJが何をしようと自分には関係ないとAは言ったが、今やその関係は強まってしまった。歳は大きく離れていないとしても、JはAの叔父になるのだから。 Aの躰に触れ、愉しんでいたマダム・ヴィーだったが、奴隷の戻りが遅いことに苛立ちを覚えはじめているようだ。 「薬はまだなの。遅い、遅すぎるわ」 その呼びかけに応じるように、部屋に人影が現れた。だが、それは奴隷ではなかった。 床に向けられた鋸から血が滴り落ちる。それを握る手――J。 夢の館専用掲示板【別窓】 |
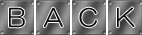
| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第11章「煉獄迷宮」 | ▲ページトップ |