| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第8章「地獄の扉」 | ノベルトップ |
| 第8章 地獄の扉 |
陽の下を生きるものたちが寝静まった頃、眼を充血させたAは部屋を出た。 少し動悸がするようだ。手にも汗を握っている。夕食から今間までの時間、とても長いものに感じられた。 閑散たる廊下。明かりすらも灯っていないその場所を、目を凝らしながら壁に手を伝いながら歩く。 テラスの先に見える月明かり。蒼い天幕が空を覆っている。 大階段を降りた時、Aは気配を感じて物陰に潜んだ。 ゆらりゆらりと揺れながら、ランプの灯火がこちらに近づいてくる。 暗闇の中からぬうっと現れた強面の男。血色が薄く、額に縫い跡があるその男は、たしか昼間あの井戸で見た大男。 見回りでもしているのだろうか、大男はランプを片手に辺りを入念に調べながら、ゆっくりと歩んでいる。 Aは大階段の裏へ行きたいが、大男に見つからないように移動しているうちに、いつの間にかまったく違う場所へと追いやられてしまった。 後ろから迫ってくる大男に気づかれぬように、足音を立てずに一本道の廊下を走るA。そのまま食堂まで来てしまった。 大男の様子を窺うと、運が悪いことに食堂に来ようとしている。さらに追い詰められてAは食堂の奥から台所へ移動した。 調理台の陰に身を潜めるが、こんな場所ではすぐに見つかってしまう。焦ったAの目に入ったのは勝手口であった。 すぐに勝手口の内鍵を開け外に飛び出した。 外に出てしまったAは目的地を変更することにした。心当たりのあるもう一つの扉だ。 月下で見るその門は、昼間よりも格段に不気味さを増していた。形を変えぬ筈の悪魔の彫刻たちが、今にも動き出しそうなくらいだ。 このマダム・ヴィーの館から、外へ通ずる巨大な正門。 さっそくAは持っている鍵を鍵穴へ差し込んでみた。だが、深く差すこともできず、鍵は半ばで止まってしまった。念のために回してみるが、やはり動かない。 扉には左右二つの鍵穴があり、さらに念のためもう片方の鍵穴にも差し込んでみるが、結果は同じだった。 「違うのか……」 その呟きは鍵穴が合わなかったことではなく、鍵を渡された理由が想像と違っていたと思ったからだ。Aはこの鍵が自分を外の世界へと解放してくれるものだと、心の片隅で期待を抱いていた。だが、門はその重い口を開くことはなかった。 疑問が再燃する。 この鍵でどこの扉を開け、そしてそこで何をしろというのか? 鍵を渡された理由が見当も付かない。Aは途方に暮れそうになりながらも、思い当たるもう一つの扉のことを考えた。そろそろ見回りも終わった頃だろうか。 しかし、その前にAには確かめたいことがあった。 さっそく月明かりを頼りにその場へ向かう。 昼間のその場所はもの悲しい場所であったが、夜のその場所は気味が悪く静まり返っている。裏庭の一画ある墓地だ。 退廃した墓石たちに囲まれ、その粗末な十字は今にも倒れそうになっていた。 Gが埋められているという墓。 そして、手向けられてた花。 花はGの墓だけでなく全ての墓に供えられていた。 感慨深い表情をしながらも、気持ちを一転させてAは木の十字架を引っこ抜き、それを使って土を掘り返しはじめた。 冷たい夜風が吹かれながらも額に汗を滲ませるA。 土は想像以上に硬い――まるで初めてその地面が掘られたように。 時間を掛けて一心不乱に土を掘り起こしていくが、何も見つからない。棺すらもその場所には埋まっていないのだ。 やがてAの手には肉刺ができ、擦り切れた傷が痺れるように痛んだ。 「……ない」 掘り進めることを諦めたAは土を戻しはじめた。 Aの掘った穴は棺を納めるには小さく、もしかしたら掘る場所がずれていた可能性も考えられたが、それはすぐに否定された。Aは土を戻しながらあることに気づいたのだ。その地面に雑草が生えていることに。 点々と生えている雑草。その隙間を掘り返した程度の小さな穴では、棺に入っていない人すら埋めることはできないだろう。やはりここには何も埋められていないのだ。 そうなるとGの屍体はどこにあるのか? なにも埋まっていないその場所に、Aは再び十字の墓標を立て、花を置いた。 刹那、その場に鬼気迫る気配がした。気づいた時にはそれが眼前まで迫っていた。 牙を剥く黒い獣。 反射的にAは横に飛び退いて地面を転がる。 鼻先に残る生臭い臭い。 それは巨大な黒犬だった。 筋骨隆々の躯が躍動し黒犬が再び牙を剥いてAに飛び掛かって来る。 犬の凶器は一つしかない。爪を狩りの道具にする猫とは違い、犬は真っ先にその牙によって獲物を仕留める。 Aは目に飛び込んできた木の墓標を手に取り、それを黒犬に噛ませた。そして空かさず犬の口を押さえる。犬の涎がAの手にこびりつく。 暴れ回る犬の力は想像以上に激しく、Aは振り回されそうになるのを必死で堪え、さらに強靱な顎の力によって開こうとする口を押さえるので精一杯だった。 そんなさなか、さらなる危機がすぐそこまで迫っていた。新たな刺客。今目の前にいる犬に加えて、さらに二匹の黒犬がAを取り囲んでいたのだ。 ここで押さえている手を離せば、すぐにでも目の前の獰猛な獣は襲い掛かってくるだろう。かと言ってこの場を離れなければほかの犬に襲われる。 危機を回避する術を失ったAに取り込んでいた二匹の犬が襲い掛かって来た。 生臭さがして噛み殺される寸前、急に犬たちが動きを止めた。それでもまだ気が立っている様子で、睨み付けるようにAを見張りながら涎を垂らしている。Aが口を押さえていた犬でさえ動きを止めてしまっている。 戸惑いながらAが辺りを見回すと、鬼火のような灯火がこちらに近づいてくる。 Aは息を呑んだ。 その場に現れたのは、あの大男だ。 地面に尻餅をつきながら全身の血を引かせているAを、大男はじっと見つめているようだった。明かりが弱くその表情まで読み取れず、言葉すら発しないために、大男が何を考えているのかわからない。 徐々に冷静さを取り戻してきたAは、失敗を犯してしまったという気持ちが募りはじめていた。こんな夜更けに、しかもこんな場所で、おそらくマダム・ヴィーの奴隷の一人であろう者に見られてしまった。このことは大男の口からマダム・ヴィーに伝えられることになるだろう。その時マダム・ヴィーはどんな反応をするのだろうか。 マダム・ヴィーはどの程度の寛容さを持ち合わせているのか、Aの立場が危うくなることは避けられないかも知れない。 大男がなんらかの合図をしたらしく、黒犬たちがAに背を向けた。そして、無言で立ち去る大男と共に闇の中へ溶けてしまった。 未だに尻餅をついているAは、手に付いた土を払いながらゆっくりと立ち上がった。 やはり勝手口から外に出たのは迂闊だったのか知れない。鍵が開いていることに気づき、大男が庭の見回りをはじめたことは十分に考えられる。 Aはまだその場から動けなかった。 これからどうするべきか、今日はおとなしく部屋に戻るべきか、それとも開き直って大胆な探索をするべきか。まだ深夜の遅い時間だ、今すぐマダム・ヴィーに報告されると決まったわけではない。こちら側が迂闊な行動に出て、相手の行動をわざわざ早める必要もない。だからと言って、おとなしく部屋に戻って運命を待つというのも、死刑執行日が決まった囚人のようだ。 もしもマダム・ヴィーへの報告が明日だった場合、それまでの時間は有効に使えるのではないか。だが、それにはこれまで以上に注意が必要になる。なぜなら、マダム・ヴィーには報告されなくても、あの大男はAを警戒している筈だ。 しかし、警戒している筈ならば、なぜこの場で何もしなかったのか。そのような権限、ないしは自由すら奴隷たちにはないのだろうか。それとも別になにかあるのだろうか。 考えれば考えるほどに先が見えなくなる。 そしてAは行動を選んだ。 足早に勝手口まで戻り、扉の取っ手を回す。鍵は掛かっていなかった。すぐに中へ入り、鍵を閉めた。 辺りに気配はない。 慎重に歩きはじめるA。ここで大男とは別の者に出くわせば、また新たな問題の火種となるだろう。もう誰にも見つかってはいけないのだ。 同じ場所に長くいることは危険だが、Aはこの場所である物を探そうとしていた。 引き出しを片っ端から開けては落胆して閉める。そして、いくつかの引き出しを開け、ついに捜し物を見つけたのだった。Aが手に取ったのはマッチだった。 向かう場所はもう決まっている。もちろん地下への扉だ。台所を抜け、食卓を抜け、廊下を歩き続ける。今のところ気配は感じられない。 さらに歩き続け大階段までやって来た。大階段の裏手は死角であり、Aは覗き込んでその場所を確かめた。誰もいない。 そして、ついに地下への扉までやって来たのだ。 ひとまずここでAは手の汗を拭い、それからあの謎の鍵を懐から取り出した。 再び手の汗を拭った。 手とは逆に唇が乾燥し、口の中はねっとりと粘つく。 鍵を握り締め、恐る恐る鍵穴に差し込む。呑まれるように鍵が鍵穴に埋まっていく。そのまま鍵は根本まで刺さった。 しばらくAは動けなかった。開くかも知れないという期待と驚きが入り交じり、極度の緊張が全身を襲ったのだ。 いったい地下に何があるというのか? 鍵がゆっくりと回される。 そして、カチッという音が静かに鳴り響いた。 「……開いた」魂が抜けるように囁いた。 扉に付いた頑丈な取っ手を引くと、重たい扉がゆっくり動きはじめ、その少し開いた隙間から冷たい風が流れ込んでくる。 人が来る前にAは扉の中へ入り、すぐさま出入り口を閉ざした。一瞬にして辺りは闇に呑まれる。すぐに先ほど手に入れたマッチに火を付ける。弱く心許ない灯火だが、すぐ近くなら見ることができる。 Aは扉を入念深く見て、そこにあった内鍵を閉めた。 そして、ついに先の見えない地下への階段を下りはじめた。 この先に進めば、鍵を渡された理由もわかり、さらにその人物も特定できるかもしれない。 一歩一歩階段を下り、周りの空気が変わっていくことを肌で感じた。湿度が高く、かび臭い。それに加えて、生臭さも漂ってくるような気がする。 階段はほどなくして終わった。それほど深い階段ではなかったが、来た道を振り返ると先は闇に呑まれている。本当にあの先に出口があるのか疑いたくなるほどだ。 廊下の幅は二メートルほど。壁や床は切り石を敷き詰められ、しっかりとした造りになっている。やはり先は見えない。 慎重に廊下を進むと、やがてT字路に差し掛かった。そこで慌ててマッチの火を消したA。片方の道から明かりが見えるのだ。 Aは片足を引いた。 引き返すべきか進むべきか迷うところだ。 まだなにも掴めていない。ここで引き返して、次の機会はあるのか。だが、先に何が待ち受けているとも知れない。 「ヒャァァァッ!」 甲高い悲鳴が鳴り響いた。 Aは心臓を鷲掴みされた気分だった。 悲鳴は明かりの方から聞こえた。男とも女ともわからない。ただあの先で怖ろしいことが起きていることだけはわかった。 Aは進んだ。重い躰を引きずるように歩き、慎重に明かりの下へ近づく。その明かりは扉から漏れた物だった。少しだけ開いたままになっている扉。まるで覗き見ることを誘っているようだ。 そっと扉の隙間に顔を近づけるA。好奇心が勝ったと言うより、見ないことの方が不安を掻き立てたのだ。 覗き見る眼の瞳孔が開いた。 部屋の中で全裸の少年が蹲っていた。まるで怯えるように、枷の嵌められた手で頭を抱えている。よく見ると足にも枷が嵌められている。 そして、その少年の背中を踏みつける紅いハイヒール。 薔薇の刺繍がされたタイツに隠された形の良い美脚。だがもう片方の脚はなく、代わりとなっていたのは松葉杖。そこにはマダム・ヴィーが立っていた。 部屋にはこのほかにも数人の女奴隷たちがマダム・ヴィーに従えていた。ここでもやはり奴隷たちはフェイスマスクで顔を隠している。その不気味さは、この状況下においていつもよりも増している。 マダム・ヴィーの艶やかな声が響く。「この子は駄目ね。仕込んでも売り物になりそうもないわ今のままでは」 奴隷たちが動きはじめる。主人の言葉の先をすでに理解しているのだ。奴隷たちによって少年は仰向けに寝かされ、身動き一つ出来ないように床に押さえつけられた。 奴隷の一人が部屋の奥に吊り下げられていた鋸を持って少年の元へ近づいてきた。 まさかとAは息を呑んだ。 少年は恐怖のあまり白目を剥きながら失禁した。 それを見て嬉しそうに嗤う濡れたルージュ。 「どこを隠したら美しく、想像を掻き立てられるかしら」 あまりにおぞましい発想だが、ある種のフェティシズムには通じている。 それは腕のないミロのヴィーナスや、腕はおろか首すらもないサモトラケのニケのように、無いことによって完成された珠玉の芸術。 人を隠された物を想像し、時に思いを馳せる。 マダム・ヴィーは顔を動かしながら足の先から丹念に少年を見ているようだった。 「足……太もも、この太ももの付け根は素晴らしいわ。ちょうどこの付け根に黒子があるのね」 皮膚はそれ自身の色が消え失せた時からフェティッシュとなる。という言葉がある。 ただ真っ白なキャンバスよりも、そこに汚れや傷があったほうが、フェティシズムの対象になりやすい。白いキャンバスに落とした一滴の黒インクは、キャンバスの白さを引き立てながら、さらにそれ自身も目を惹き魅力的である。 「両腕を切断しましょう。そうね、肩から十五センチくらいのところがいいわ」 マダム・ヴィーの言葉を聞いてなんの躊躇いもなく、奴隷が鋸を少年の上に押し当てた。 そして――。 Aはそれ以上見ていることができなかった。 その場から足早に逃げるAの背中に、地獄の絶叫が針のよう降り注いだ。 暗闇の中を壁を手で探りながら小走りで進んでいたAは、途中で思い出したようにマッチに火を点けた。壁を擦っていた手のひらは皮が剥け血が滲んでいた。そのことにすら今気づいた。 先の見えない階段を上る。行きに通った道だというのに、今では全く違う道に思える。もしかしたら、扉を開いた先には別の世界が広がっているのではなかろうか。そんな幻覚すら頭を過ぎってしまう。 気づけば扉は目の前にある。 固く閉ざされた扉をAは必死になって押した。何度押しても、どんなに力を込めて開かない。後ろから追いかけてくる恐怖で発狂しそうになりながらも、Aは必死でそれを堪えてようやく気づいた――内鍵が掛かっていることに。 慌ててAは鍵を開け、そのまま扉を力一杯押して外に飛び出した。 扉を出来るだけ静かに閉め、その場から逃げようとして足を踏み出し、扉に鍵をかけ忘れたことに気づいて足を戻した。 鍵をどこにしまったのか思い出せない。ポケットや懐を順に調べて、やっと鍵を見つけて扉に鍵を掛けた。 そして、歩き出そうと振り向いたその先に――大男は立っていた。 何も言わずただAのことを見つめている。 その瞳はとても物悲しく、口は何かを言いたげに震えている。 混乱に陥っているAは言い逃れの言葉すら出ず、ただその場から逃げることしかできなかった。 夢の館専用掲示板【別窓】 |
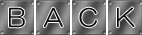
| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第8章「地獄の扉」 | ▲ページトップ |