| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第7章「謎の鍵」 | ノベルトップ |
| 第7章 謎の鍵 |
そこには燃えるような真っ赤なルージュ。 目を覚ましたAは驚きのあまり蛇に睨まれた蛙のように、躰がすくんで動かなくなってしまった。 ベッドに横たわるAの顔を覗き込んでいたのはマダム・ヴィーの視線。彼女は車椅子から身を乗り出し、愛でるような瞳でAを舐め回すように見つめていた。 「お目覚めね。ワインでもいかが?」 ルージュから発せられた言葉を寝起きのAは理解するのに時間を要した。 「いえ、それよりも……ここは?」 自分が使っている部屋とは違う場所。 部屋は煌びやかに装飾され、嫌みなほど豪華絢爛な部屋であった。性格に例えるなら傲慢。部屋の主を表しているようであった。 「わたくしの部屋よ」 答えを聞かずとも、すでに察しはついていた。そのことよりも、ここがマダム・ヴィーの部屋だとするならば、なぜここにいるのかということのほうが問題だ。 ここで目覚める前に残っている最後の記憶。それは蒼いベールから覗く哀しげな二つの瞳。そうだ、AはMの部屋にいた筈であった。 明らかに不自然な気の失い方。さらにはマダム・ヴィーの元へ連れてこられた。まさかMにはマダム・ヴィーの息が掛かっているのか。だが、取り巻く環境を考えれば、誰もが信用ならず、マダム・ヴィーの影響下にあるような気がする。 Aは何を質問するべきか迷っていた。自分がここにいる理由を問うことは危険を孕んではいないだろうか。だが、この不自然な状況を聞かぬ方がそれこそ不自然ではなかろうか。 「僕はなぜここにいるのですか?」 「昏倒して気を失った貴方の様態を診るため、わたくしの元へ運ばれてきたのよ」 「医学の知識がおありで?」 「ええ、少しばかり」 この時、Aはケシ畑のことを思い出していた。ケシから生成されるモルヒネは麻酔薬として使われる。だがそれだけの理由で、裏庭で〝麻薬〟にも使われる植物を栽培するだろうか。 「それで何か僕に異常は見つかりましたか?」Aが尋ねると頭を振った。 「いえ、外的な症状は特出して目立った異変は診られなかったわ。ただ少し疲れているだけでしょう。今も蒼くやつれた顔をしているわ――まるで悪魔を目の前にしているような」そう言ってマダム・ヴィーは含み笑いをした。 Aは取り直そうとして柔和な表情を作ろうとしたが、強ばった頬が言うことを利かない。そんなAの表情を読み取った様子のマダム・ヴィーは、気分を害するどころか喜んでいるようだった。精神的に嬲りことをおもしろがっているようにも見える。 少しずつだがAは落ち着きを取り戻していた。そして、マダム・ヴィーと二人っきりで話をするまたとない機会であることを察した。 「つかぬ事をお伺いいたしますが、Gから僕のことをなにか聞いていないでしょうか。僕の意識がない間にGが、皆さんにどのように僕のことを紹介したのか気になってしまって」 「特になにも聞いていないわ。この屋敷では人の素性を詮索するような無粋な者はいないもの」一呼吸置いて、「この意味がおわかり?」 Aは背筋をぞっとさせた。 マダム・ヴィーはAが詮索をしていることに気づいているのだろうか。二号からいくばくかの話を聞いているかもれない。 相手がどこまで知り得ているのか、それによってカードの切り方が変わってくる。投げかける質問は慎重でなくてならない。たとえ尋ねたいことが山のようにあろうと、焦ってはいけない。 地下室へ近づくことは容易に許されてはいないが、それ以外の場所の立ち入りについて忠告を受けた覚えはない。だとしたら庭の散策で不都合なものを見られることはないと言うことだろうか。 一か八かAは質問を投げかける。 「そう言えば、今日は庭を拝見させていただいたのですが、裏庭に少し臭いは強いですが赤く美しい花が咲いていました。あれはなんという花でしょうか?」知っていることをあえて尋ねた。 「ケシの花よ。モルヒネ、そしてアヘンの材料になるわ」 「ああ、あれがケシなのですか。友人がアヘン窟に通っていたのを思い出しました」 「貴方もアヘンを?」 「いえ、僕は……」 Aはもう少し踏み込むべきか迷っていた。本当に聞きたいことはケシの話ではない、そのケシ畑の近くにあった〝モノ〟だ。 ――やはり聞くことは出来なかった。代わりに違う方向から訊くことにした。 「ところでGの亡骸はどうなりましたか? もう埋めてしまったのでしょうか、できれば墓地に祈りを捧げてやりたいのですが」 「ええ、裏庭の一画に急ごしらえだけれど埋葬したわ。数日後には整然とした墓ができあがるでしょう」 「あの場所に案内してもらいたいのですが?」 「あとで奴隷に言い付けて置くわ」 「ありがとうございます」 Aは深い礼をしたあと、ベッドから降りようとしたのだが、その胸板をマダム・ヴィーの手袋をした繊手が強く押した。 「まだお休みなさい」 「いえ、もう大丈夫です」 「本当にそうかしら?」 繊手で首筋をなぞられたAは身を震わせ、次の瞬間には全身から力が抜けてしまっていた。 熟れた真っ赤なルージュが迫ってくる。それは果実と言うより炎。全てを喰い尽くす紅蓮の業火。 Aは本能で恐怖を感じた。 脳が揺さぶられる。 酷い頭痛を感じたAはその場で身悶えた。 脂汗を掻きながら一欠片の精神力を振り絞ってAはこの場から逃げようとした。この状況から逃げることで、マダム・ヴィーの機嫌を損ねることにならないか。そのようなことなど考える余裕もなく、ただ逃げようとした。 「もう大丈夫です……失礼……します」 激しい呼吸の合間に途切れ途切れで発せられた言葉。明らかに様子がおかしく、それを相手が察しない筈もないが、構わず余裕もなくAはベッドから這い起きて部屋を飛び出した。 マダム・ヴィーは追いかけてこなかった。そのそぶりすら見せなかった。 どうにか部屋の外に逃げ出したAをそこで待っていたのは、Jの姿。彼は心配そうな口元を露呈していた。 「どうかしたのかい?」 「いや……」 口では否定しながらも、躰の均衡を崩して倒れそうになったAをJが抱きかかえ、肩を貸してしっかりと立たせた。 「顔色が悪く酷い汗だ。部屋まで送ろう」 「……すまない」 もはやAはひとりで歩くこともままならない状態だった。 部屋に向かいながら多少の落ち着きを取り戻し、Aの思考にも余裕が生まれた。 「なぜマダム・ヴィーの部屋の前に?」 「たまたま通りかかっただけさ」 「嘘だ。貴方はおそらくしばらく前から部屋の前にいた、理由はわからないが」 「理由などないさ。ボクはたまたま通りかかっただけだからね」 Jの目的や真意を問いたかったが、はぐらかされるの落ちだろう。今はそれを問うことを諦め、Aは別の質問を投げかけることにした。 「この屋敷ではアヘンを扱っているのですか? たとえば、貴方もその客の一人。貴方自身は吸わないとしても、貿易関係の仕事をしていると言っていましたが、それはアヘン貿易のことでは?」 「客……好い線を行っているが、アヘンは余興に過ぎない。少なくとも遊技としてはね」 「余興? 遊技としては?」 「マダム・ヴィーの財源の一つであったとしても、彼女にとってアヘンは嗜好品としての価値はそれほど高くはないということさ」 ならば余興の先にもっと価値あるモノがあるということか? 歩いて進むうちに今いる場所が大階段の裏であることにAは気づいた。 「こちらにも道があったのか」 「奥まった場所にあるので気づきづらいね。この屋敷はT字になっているけれど、二階はそうではなく長方形になっているのだよ」 そして、大階段の真裏には大きな扉があった。 「その扉は?」Aは尋ねた。 「ふふ、地獄の扉……というのは冗談で、ただの地下への階段さ」悪戯なJの口元。なぜか冗談には思えない雰囲気を醸し出していた。 やがて階段を上り廊下を進み、Aの部屋の前までやって来た。 Aは借りていた肩を返してJから離れた。 「ここまでで結構です。ありがとう」 しかし、Jの手は急にAの腰に廻され、瞬く間に抱き寄られてしまっていた。 「まだ心配だ。ベッドまでお付き合いしよう」 マスクの下から覗くJの熱っぽい視線。 耐えかねてAはJを突き飛ばそうとしたが、それよりも早くJはさっと身を引いた。 そして、この場に現れた二号。 「お館様のお言いつけで参りました。A様のご様態をお館様は案じております。それからG様の墓までの案内を申しつけられております」 二号の出現にJは軽い会釈だけしてこの場から風のように立ち去ってしまった。 Aは手の汗をズボンで拭いながら、二号への受け答えを考えた。その時、Aはあることに気づいた。ズボンのポケットになにか硬い物が入っている。だが、その場では確認せずに何食わぬ顔をした。 「少し気分は優れないが、お気遣いは必要ない。Gの墓へはまた今度にするとしよう。あぁ、それから夕食は自分の部屋でゆっくりと摂りたいのだが?」 「かしこまりました。夕食はお部屋までお運びいたします」 「ありがとう」 なぜかその時、二号の瞳は戸惑うように揺れ動いていた。 「どうかしたのか?」 「いえ、なにもございません」 「本当に?」 「お礼の言葉を言ってくださるのは、A様とJ様だけのものですから」 会釈をして二号は逃げるように立ち去ってしまった。 さっそく部屋の中に入ったAはポケットの中を確かめた。中に入っていたのは鍵。とても大きな物で、これを使用する扉も大きなことが予想される。 いったいどの扉の鍵なのか? そして、どうのような経緯でAのポケットに入ったのか? 経緯については、Aに記憶がないのなら、何者かが混入させたと考えるのは自然だろう。 では、いったい誰が? いつ混入されたのか考えながら、Aは時間を遡った。最後に会ったのは二号だが、鍵を入れられるほど至近距離まで近づいていない。だとするならば、J、そしてマダム・ヴィーが怪しいことになる。その二人にとりあえず絞り、別の方向から二人に繋がる点はないかと考える。 わざわざ鍵を渡すということは、どこかの扉を開けろということだ。その扉を突き止めることにより、自ずと人物が見えてくるかも知れない。 この鍵が合うような大きな鍵穴を持つ扉。Aには三つの心当たりがあった。正門、玄関、地下への扉。このうち玄関は元々出入りが規制されているわけではないので、残る二つに絞ることができる。 推測は一つの可能性。実証をしてみなければ答えはわからない。だが、試すにしても機会を窺わなくてはいけない。 いつの間にか気分もだいぶ良くなっていた。そのため、Aはさっそく扉を探しに行くことにしたのだった。 目的もなく無意味に屋敷を歩き回ることでさえ、何かしら危険を感じるというのに、扉を探すことはどこか後ろめたさ、もしくは危険を孕んでいるのではないだろうか。 急にAは立ち眩みを覚えた。脳裏にはマダム・ヴィーのルージュ。 彼女は詮索されることを好まないらしい。ならばやはり扉を探すことは、知られてはいけない。だが、万が一、彼女が鍵の送り主だったとしたら? まるで手招きされているような……。そうだとしたらぞっとする。それでもAは行動をやめなかった。 大階段の近くまでやって来た。ここから先は人と出会いたくはない。周りに人がいないことを確かめていた時、大階段の裏から二号が姿を現した。もしも慎重を期せず足を踏み入れていたら、言い訳の苦難することであった。 二号はAを確認した立ち止まった。 「ご気分はもう宜しいのですか?」 「ああ、だいぶ良くなったみたいだ。そうだ、ここであったのはちょうど良い、Gの墓へ案内してくれないか?」 扉を探すことは一時取りやめだ。 「かしこまりました。こちらでございます」 歩き出した二号に付いてAも歩き出した。 二人は玄関を出て裏庭に向かった。その道筋はAが通ったことにない経路。辿り着いた場所も来たことになかった場所だった。 そこには崩れかけ、おそらく放置されているのであろう墓石がいくつかあった。同じ場所にGが埋まられていると考えると、たとえ親しみなどなくともAは哀れな気分になった。 Gの墓にはまだ墓石はなく、十字に組み合わせれた木が立ててあるのみだった。 膝を突いてAは指を組んで祈りを捧げた。 立ち上がったAは辺りを見回しながら墓石について尋ねる。 「あの墓は誰の?」 「存じ上げません」 「存じ上げない? この家の者の墓ではないのか?」 「お館様からはなにも聞かされておりません」 本当にそうなのかもしれない。墓の荒れようを見れば、マダム・ヴィーがこの墓にどのような思いを抱いているのかおおよその察しはつく。もしかしたら思いすらないかもしれない。 「一つ頼みを聞いてくれないか?」もの哀しげな声音でAが囁いた。 「なんなりと」 「時間の空いた時でいい。墓に花を手向けてやってくれないか。Gの墓だけでなくほかの墓にも」 二号は明らかに言葉に詰まり戸惑っている様子だった。 しかし、「かしこまりました」と小さく頷いた。 そしてAは「ありがとう」と呟いた。 夢の館専用掲示板【別窓】 |
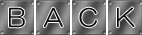
| ■ サイトトップ > ノベル > 夢の館 > 第7章「謎の鍵」 | ▲ページトップ |